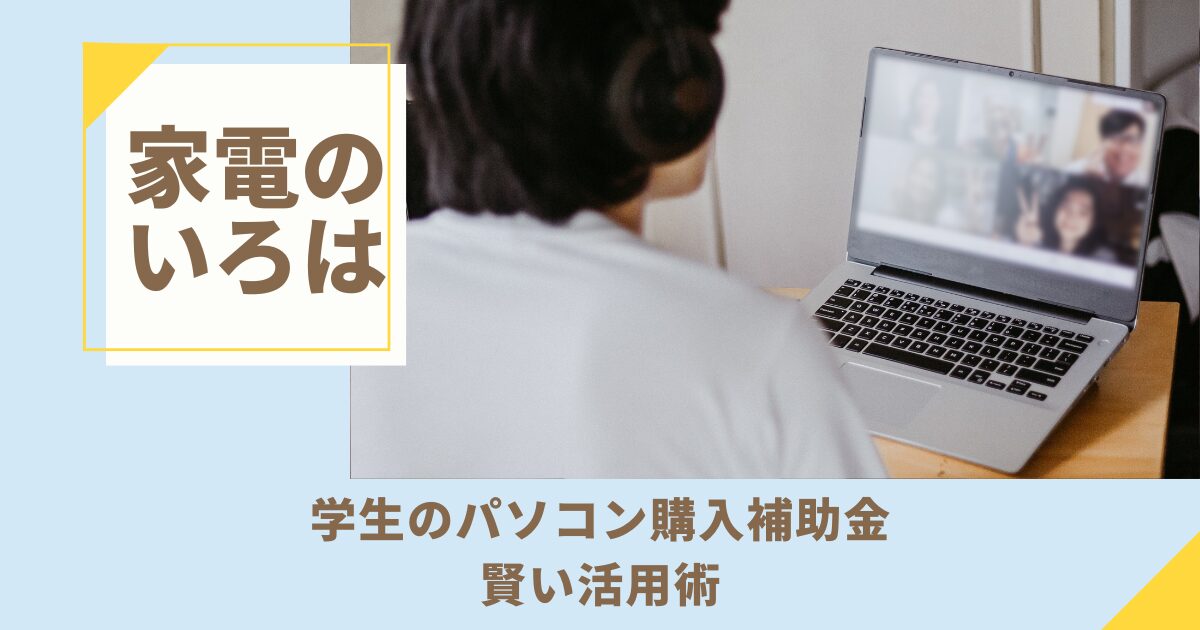「大学のオンライン授業でパソコンが必須になった…」
「高校入学に合わせて新しいPCが欲しいけど、費用が高くて…」
「学生が使えるパソコン購入の補助金って、本当にあるの?」
新しい学びのステージに進む学生の皆さん、そしてそれを支える保護者の皆さん。パソコンは今や学習に欠かせないツールですが、その購入費用は決して安くありませんよね。
もし、その負担を少しでも軽くできる制度があるとしたら、知りたくありませんか?
ご安心ください。実は、学生向けのパソコン購入を支援する補助金や助成制度は、国や自治体、大学などで用意されています。しかし、その情報は点在しており、自分に合った制度を見つけ出すのは一苦労です。
この記事では、高校生向け、大学生向けの補助金制度から、申請方法、さらには補助金で購入できるおすすめのパソコンまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたのパソコン購入に関する費用の悩みが解決し、賢くお得に最新の学習環境を手に入れる方法がすべて分かります。
Amazonで人気の「パソコン」を見る楽天市場で人気の「パソコン」を見る
結論:学生向けパソコン購入補助金は存在する!

まず、皆さんが最も知りたいであろう結論からお伝えします。
はい、高校生や大学生を対象としたパソコン購入に関する補助金・支援制度は存在します。
ただし、誰でも無条件に受けられるわけではなく、支援元(国、自治体、学校など)によって対象者や条件、金額が大きく異なります。まずは、どのような制度があるのか全体像を把握することが重要です。

補助金・支援制度の種類と実施主体
学生向けのパソコン購入支援は、主に以下の機関によって実施されています。
| 実施主体 | 制度の概要・特徴 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 国 | 全国の学生を対象とした大規模な支援。経済的に困難な学生を対象とすることが多い。(例:学生支援緊急給付金など) | 大学生・専門学生など |
| 自治体(都道府県・市区町村) | その地域に在住する学生が対象。制度の有無や内容は自治体によって大きく異なる。新入生向けが多い傾向。 | 高校生・大学生 |
| 学校(大学・高校) | 在籍する学生のみが対象。独自の奨学金や貸与制度、購入補助などがある。パソコン必携化に伴い制度を設ける大学が増加中。 | 高校生・大学生 |
| 大学生活協同組合(生協) | 組合員(学生)向けの割引や購入補助。期間限定で募集することが多い。 | 大学生 |
| 民間団体・企業 | 特定の条件を満たす学生を対象とした給付型奨学金など。パソコン購入費に充当できる場合がある。 | 高校生・大学生 |
このように、支援の形は様々です。次の章から、「高校生向け」と「大学生向け」に分けて、さらに詳しく掘り下げていきましょう。
高校生向け:タブレット・パソコン購入補助金を解説

近年、GIGAスクール構想などを背景に、高校でもデジタル端末の活用が急速に進んでいます。それに伴い、新入学の高校生を対象としたパソコンやタブレットの購入補助金制度を設ける自治体が増えています。
ここでは、高校生向けの補助金制度について、その概要から申請方法までを徹底的に解説します。
高校生向け補助金制度の概要
教育のデジタル化は、生徒たちの学習機会を広げる一方で、各家庭に経済的な負担を強いる側面もありますよね。この負担を軽減し、すべての生徒が平等な学習環境を得られるようにすることが、この制度の主な目的です。
制度のポイントを以下にまとめました。
- 支給金額:平均で1万円〜5万円程度が相場です。
- 対象者:主に新入学の高校生が中心となります。
- 対象機種:基本的な学習(オンライン授業、レポート作成など)に必要な機能を備えたモデルが想定されています。
- 所得制限:多くの制度で、世帯収入による所得制限が設けられています。
- 地域差:お住まいの自治体によって制度の有無や内容が大きく異なります。

補助金を受けるための申請条件と対象者
補助金を受けるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。一般的に、経済的な支援を特に必要とする家庭が優先される傾向にあります。
具体的な申請条件をチェックリスト形式で見ていきましょう。
- ✅ 世帯収入が一定の基準以下であること
これが最も重要な条件の一つです。基準額は自治体によって定められており、住民税非課税世帯などが対象となることが多いです。 - ✅ 高校に在籍中、または入学予定であること
新年度に高校へ進学する生徒や、既に在学中の生徒が対象です。 - ✅ 保護者の同意が得られていること
申請は基本的に保護者が行います。 - ✅ 在住の自治体が制度を実施していること
大前提として、お住まいの市区町村や都道府県に制度がなければ申請できません。
また、申請には以下の書類が必要となる場合がほとんどです。事前に準備しておくと手続きがスムーズに進みます。
- 住民票(世帯全員が記載されたもの)
- 収入証明書(課税証明書や源泉徴収票など)
- 学校の在学証明書や合格通知書
- 学校からの推薦状(求められる場合もあり)
これらの条件や必要書類をしっかり把握し、準備を進めることが、補助金を賢く活用するための鍵となります。
パソコン購入補助金の申請方法と手続きの流れ
「手続きって難しそう…」と感じるかもしれませんが、流れを掴んでしまえば大丈夫です。一般的な申請から受給までのステップを解説します。
- 【情報収集】自治体や学校の公式サイトで対象制度を確認
まずは、お住まいの市区町村のホームページや、入学予定の高校の公式サイトを確認します。「教育委員会」や「就学支援」といったページに情報が掲載されていることが多いです。 - 【書類準備】必要書類を揃える
上記の「収入証明書」や「住民票」などを準備します。役所で発行してもらう書類は時間がかかる場合があるので、早めに動き出しましょう。 - 【申請書記入・提出】申請書を記入し、オンラインまたは郵送で提出
申請書を公式サイトからダウンロードし、必要事項を記入します。最近はオンラインで完結する自治体も増えていますが、郵送のみの場合もあります。申請期限は厳守です! - 【審査】申請後に審査が行われる
提出された書類を基に、自治体や学校が受給対象となるかどうかの審査を行います。 - 【結果通知・受給】承認されれば、指定口座に補助金が振り込まれる
審査に通ると、決定通知書が届きます。その後、指定した保護者の口座に補助金が振り込まれるのが一般的です。振込時期は申請から1〜2ヶ月後が目安です。

大学生向け:パソコン購入で利用できる補助金・支援制度

続いて、大学生向けの支援制度を見ていきましょう。大学生の場合、高校生とは少し状況が異なり、「大学」や「生協」が主体となる独自の支援が中心となります。
政府からの直接的な補助金は限定的
まず知っておきたいのは、現状、政府から「大学生のパソコン購入費用」として直接支給される補助金制度は、恒常的には設けられていないという点です。
過去には、コロナ禍における経済支援として「学生支援緊急給付金」のような制度がありましたが、これは学業継続が困難な学生全般を対象としたもので、パソコン購入に限定されたものではありませんでした。
そのため、大学生がパソコン購入の支援を探す場合、国よりも、自分が在籍する大学に目を向けることが最も重要です。
メインは「大学・生協」の独自補助制度!
近年、多くの大学でオンライン授業が導入され、パソコンが必携となっています。この流れを受け、大学や大学生活協同組合(生協)が、学生の負担を軽減するために独自の購入補助制度を設けるケースが増えています。
ここでは、具体的な事例として「北九州市立大学生活協同組合(北九大生協)」の2025年度の例を見てみましょう。
【事例】北九大生協のパソコン購入費補助支援
- 補助額:一人 5万円
- 定員:7名
- 対象パソコン:生協が指定する特定のモデル(富士通 UH08/J3など)
- 申請方法:専用のWebフォームから申し込み
- 選考方法:提出された申請理由(収入証明書や奨学金受給証明書などを添付)を基に、生協の委員会が選考
- 受付期間:総合型選抜、一般入試(前期・後期)など、入試区分ごとに細かく設定
この事例から分かるように、大学・生協の制度には以下のような特徴があります。
- 定員が限られている(選考あり)
- 補助額が比較的高額(5万円など)
- 対象となるパソコンの機種が指定されている場合がある
- 申請期間が短い(特に新入生向け)
- 日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金受給者などが優先される傾向がある
自分の大学の制度を探す具体的な方法
「じゃあ、自分の大学にそんな制度があるか、どうやって調べればいいの?」と思いますよね。以下の3つの方法を試してみてください。
- 大学の公式サイトをチェックする
「お知らせ」「学生生活」「奨学金・経済支援」などのページを確認しましょう。「PC」「パソコン」「購入補助」といったキーワードでサイト内検索するのも有効です。 - 学生課や担当部署に問い合わせる
新入生の場合は入学手続きの書類に案内が入っていることもあります。在学生の場合は、学生課や情報センターなどの窓口で直接聞いてみるのが確実です。 - 大学の生協サイトを確認する
生協がある大学の場合、新入生向けの「入学準備サイト」などでパソコンの販売と合わせて補助制度の案内をしていることが多いです。見逃さないようにしましょう。
個人で申請できる!パソコン購入補助金はある?

「学生」という枠組みだけでなく、「個人」として申請できるパソコン購入補助金についても気になりますよね。特に社会人学生や、特定の条件に当てはまらない方にとっては重要な情報です。
結論から言うと、個人が汎用的に使えるパソコン購入専用の補助金は、非常に少ないのが現状です。
多くの場合、補助金は「子育て支援」「就労支援」「障がい者支援」といった、より大きな目的の一部として提供されます。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- ひとり親家庭向けの就労支援金の一部を、スキルアップのためのパソコン購入に充てることができる。
- 生活困窮者自立支援制度の中で、就職活動に必要なパソコンの購入費用が補助されることがある。
- 障がいのある方向けの日常生活用具給付等事業で、特定の機能を持つパソコンが給付対象となることがある。
もしご自身が何らかの支援制度の対象となる可能性がある場合は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口などに相談してみることをお勧めします。「パソコンが欲しい」という目的だけでなく、「〇〇のためにパソコンが必要です」と具体的な理由を伝えることが大切です。
「10万円のパソコン助成金」は本当?噂の真相

インターネットで検索していると、「パソコン 助成金 10万円」といった魅力的なキーワードを目にすることがあります。まるで、申請すれば誰もが10万円をもらえるかのような印象を受けますが、これは本当なのでしょうか?
結論:学生向けに一律10万円の助成金は「ない」
残念ながら、学生を対象にパソコン購入費用として一律10万円が支給されるような国の助成金制度は存在しません。
この「10万円」という数字は、おそらく過去に実施された「特別定額給付金」や、事業主向けの「IT導入補助金」などの情報と混同されている可能性が高いです。これらは目的も対象者も全く異なる制度です。

高額な支援が必要な場合の代替案
もし、補助金だけでは購入費用が足りず、まとまった金額が必要な場合は、以下のような制度の活用も検討してみましょう。
- 奨学金制度:日本学生支援機構(JASSO)の奨学金など。給付型(返済不要)と貸与型(返済必要)があります。
- 教育ローン:国(日本政策金融公庫)や民間の金融機関が提供しています。奨学金よりも金利は高めですが、必要なタイミングで借りやすいメリットがあります。
- 大学独自の授業料減免制度:経済的な理由で修学が困難な学生に対し、授業料の一部または全部を免除する制度です。浮いた費用をパソコン購入に充てるという考え方もできます。
まずは大学の学生課などで、利用できる制度がないか相談してみることをお勧めします。
補助金で買える!学生におすすめのパソコン3選

さて、ここまで補助金制度について詳しく見てきましたが、「実際にどんなパソコンが買えるの?」という疑問が湧いてきますよね。
補助金の相場である5万円から8万円程度の価格帯を想定し、学生の皆さんに心からおすすめできるパソコンを3つのモデルに厳選してご紹介します。パソコン選びで失敗したくない方は必見です!
学生のパソコン選びで失敗しないための5つのポイント
おすすめモデルを紹介する前に、まずはパソコン選びの基準をお伝えします。以下の5つのポイントを押さえておけば、大きく失敗することはありません。
- 【軽さとバッテリー】持ち運びは正義!
大学のキャンパス内で持ち運ぶなら、本体重量は1.3kg以下が理想。また、コンセントを探し回らなくて済むよう、バッテリー駆動時間は最低でも8時間以上のものを選びましょう。 - 【スペック】「メモリ8GB」が最低ライン
複数のソフトを同時に動かすことも多い大学生活。快適に作業するなら、処理の速さに関わるメモリは最低8GB、できれば16GBあると安心です。保存容量(ストレージ)はSSD 256GB以上が目安です。 - 【大学の推奨スペック】必ず確認しよう!
特に理系学部やデザイン系の学部では、専門ソフトを使うために高いスペックが求められることがあります。入学案内の資料や大学のサイトで「推奨スペック」が公開されていないか、必ず確認してください。 - 【OS】WindowsかMacか、それとも…?
多くの大学ではWindowsが主流ですが、デザイン系ならMacが指定されることも。迷ったら、周りの学生や先輩が多く使っているOSを選ぶのが無難です。最近では、安価で起動が速いChromeOSも選択肢に入ります。 - 【保証とサポート】4年間の安心を買う
大学生活4年間、ずっと使い続ける大切なパートナーです。万が一の故障に備え、メーカーの保証期間が長いモデルや、動産保険などのオプションを検討しましょう。
おすすめモデル1:【コスパ最強】Chromebook
| モデル名 | 各種メーカー Chromebook |
|---|---|
| 価格帯 | 約4万円〜7万円 |
| 特徴 | ✅ 圧倒的な起動の速さ ✅ 軽量・長時間バッテリー ✅ Google系アプリとの連携がスムーズ ✅ ウイルス対策ソフトが不要で安全 |
レポート作成やオンライン授業、Webでの調べ物がメインなら、Chromebookは最高の選択肢です。
WindowsやMacとは異なる「ChromeOS」を搭載しており、動作が非常に軽快なのが最大の特徴。電源ボタンを押してから数秒で起動し、すぐに作業を始められます。データは基本的にGoogleドライブなどのクラウド上に保存するため、パソコン本体の容量を圧迫しにくく、万が一パソコンが壊れてもデータは安全です。
特に、大学でGoogle Workspace(Gmail, Googleドキュメント, スプレッドシートなど)を多用するなら、これ以上ないほど快適な連携を体験できるでしょう。価格も比較的安価なモデルが多く、補助金の範囲内で十分高性能なモデルが手に入ります。
ただし、注意点もあります。Windows用の専門的なソフトウェア(例:一部の統計解析ソフトやCADソフト)は基本的に使えません。ご自身の学部で特殊なソフトが必要かどうか、事前に確認が必要です。
おすすめモデル2:【万能優等生】Lenovo IdeaPadシリーズ
| モデル名 | Lenovo IdeaPad Slim シリーズ |
|---|---|
| 価格帯 | 約6万円〜9万円 |
| 特徴 | ✅ シンプルで洗練されたデザイン ✅ 高性能CPU搭載モデルも選択可能 ✅ キーボードが打ちやすいと評判 ✅ コストパフォーマンスが非常に高い |
「Windowsパソコンがいいけど、価格は抑えたい。でも性能には妥協したくない!」そんなわがままな願いを叶えてくれるのが、LenovoのIdeaPadシリーズです。
世界的なPCメーカーであるLenovoが作るだけあって、その品質は折り紙付き。特にキーボードの打鍵感には定評があり、長時間のレポート作成でも疲れにくいと学生から高い支持を得ています。
この価格帯でありながら、最新のCPUを搭載したモデルや、メモリを16GB搭載したモデルも選択肢に入ってくるのが最大の魅力。オンライン授業はもちろん、少し重たい作業やプログラミング学習にも十分対応できるポテンシャルを秘めています。まさに「万能優等生」と呼ぶにふさわしい一台で、4年間安心して使えるパートナーになるでしょう。
頻繁にセールを行っているのも嬉しいポイント。公式サイトの「学生ストア」を利用すれば、さらにお得に購入できる可能性がありますので、ぜひチェックしてみてください。
おすすめモデル3:【安心の国内メーカー】富士通 FMV / NEC LAVIE
| モデル名 | 富士通 FMVシリーズ / NEC LAVIEシリーズ |
|---|---|
| 価格帯 | 約7万円〜10万円 |
| 特徴 | ✅ 高い信頼性と堅牢な作り ✅ 国内メーカーならではの手厚いサポート体制 ✅ 日本語入力の快適さや便利な独自ソフト ✅ 親世代にも馴染みがあり安心感が高い |
「初めての自分のパソコンだから、やっぱり安心できるメーカーがいい」という方には、日本の誇る富士通やNECがおすすめです。
海外メーカーに比べて価格は少し高めになりますが、その分、品質管理が徹底されており、故障しにくい堅牢な作りが魅力です。万が一トラブルが起きても、国内にサポート拠点があるため、電話やチャットでの相談がしやすく、修理対応もスムーズです。この「いざという時の安心感」は、他のメーカーにはない大きなアドバンテージと言えるでしょう。
また、長年日本語と向き合ってきたメーカーだからこその、日本語入力システムの優秀さも特筆すべき点です。予測変換の精度が高く、ストレスのない文章作成が可能です。パソコン操作に不慣れな方でも迷わず使えるような、親切なナビゲーションソフトがプリインストールされていることも多く、まさに「パソコン初心者」に優しい設計となっています。
Amazonで人気の「パソコン」を見る楽天市場で人気の「パソコン」を見る
よくある質問(Q&A)

最後に、学生の皆さんや保護者の方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。疑問点の解消にお役立てください。
A1. 原則として保護者が行います。特に高校生向けの制度では、保護者の収入証明などが必要となるため、保護者名義での申請が基本となります。大学生向けの制度でも、未成年の場合は保護者の同意が必要です。
A2. 制度によって異なりますが、申請締め切り後、1ヶ月〜2ヶ月程度で指定の口座に振り込まれるケースが多いです。パソコンを購入した後の「後払い」形式となることが一般的なので、一度は購入費用を立て替える必要がある点に注意してください。
A3. 自己負担が一部発生することが多いです。補助額は1万円〜5万円が相場ですが、学生生活で4年間快適に使えるパソコンは6万円〜10万円程度の価格帯が中心です。補助金はあくまで「購入費用の一部を支援するもの」と考え、不足分は自己資金で準備する必要があります。
A4. 一般的には対象外となるケースがほとんどです。多くの補助金制度では、新品のパソコンを購入した際の領収書の提出が求められます。フリマアプリや個人間売買での購入はもちろん、中古販売店での購入も対象にならない可能性が高いので、必ず事前に募集要項を確認してください。
A5. 何よりも「申請期限」です。多くの制度、特に新入生向けのものは申請期間が非常に短く設定されています。「気づいた時には終わっていた…」ということがないよう、合格が決まったらすぐにアンテナを張り、情報収集を始めることが重要です。また、提出書類に不備があると審査対象外になることもあるため、念入りに確認しましょう。
まとめ:情報を制して、賢くパソコンを手に入れよう!

今回は、学生向けのパソコン購入補助金について、高校生・大学生それぞれのケースや申請方法、おすすめのパソコンまで、網羅的に解説してきました。
最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- ✅ 学生向けのパソコン購入補助金は「存在する」が、支援元は国・自治体・大学など様々。
- ✅ 【高校生】お住まいの自治体の制度が中心。所得制限がある場合が多い。
- ✅ 【大学生】在籍する大学や生協の独自制度が中心。定員制で選考がある場合が多い。
- ✅ 申請には収入証明書などが必要。何よりも「申請期限」を厳守することが重要。
- ✅ 補助金の相場(5〜8万円)でも、ChromebookやLenovo IdeaPadなど高性能なPCは十分に購入可能。
新しいパソコンは、あなたの学びの可能性を無限に広げてくれる強力なツールです。しかし、その購入費用が夢への一歩をためらわせる足かせになってはいけません。
今回ご紹介した情報が、あなたの経済的な負担を少しでも軽くし、快適な学生生活をスタートさせるための一助となれば幸いです。
さあ、まずはご自身の自治体や大学の公式サイトをチェックすることから始めてみましょう!
あなたにぴったりの支援制度を見つけて、賢くお得に最高の学習環境を手に入れてくださいね。
Amazonで人気の「パソコン」を見る楽天市場で人気の「パソコン」を見る