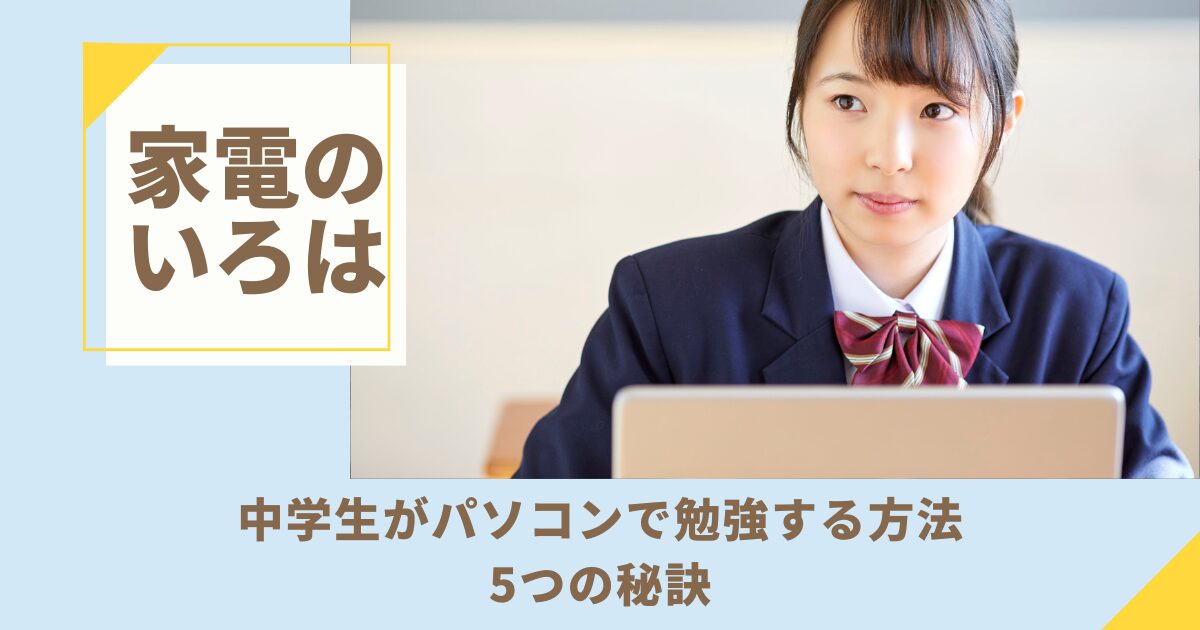「周りの友達がパソコンで勉強してるけど、具体的にどうやるの?」
「今年はいよいよ受験。パソコンを使ってもっと効率的に勉強したい!」
「スマホやタブレットじゃダメなの?パソコンならではの勉強法が知りたい!」
そんな悩みを抱えている中学生のあなたへ。
この記事では、中学生がパソコンを使って成績を上げるための具体的な勉強法を、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。
実は、パソコンを使った勉強は、ただ動画を見るだけではありません。計画を立てたり、レポートを作成したり、さらには将来役立つスキルを身につけたりと、あなたの可能性を無限に広げてくれる最高のツールなんです。
この記事を最後まで読めば、以下のことが分かります。
- パソコンで勉強する本当のメリット
- 明日から実践できる具体的な勉強ステップ
- 無料で使えるおすすめの学習サービスやアプリ
- 勉強に集中するためのコツや注意点
紙のノートとペンでの勉強に、パソコンという強力な武器をプラスして、ライバルに差をつけましょう!
なぜ今、中学生にパソコンでの勉強がおすすめなのか?
「スマホでも動画は見れるし、わざわざパソコンじゃなくても…」と思うかもしれません。しかし、パソコンにはスマホやタブレットにはない、学習効果を最大化するメリットがたくさんあります。まずは、その理由から見ていきましょう。

理由1:勉強の効率が劇的に上がる
パソコンの最大のメリットは、情報処理能力の高さです。調べ物をするとき、複数のサイトを同時に開いて情報を比較したり、Wordでまとめながら重要な部分をコピー&ペーストしたりできます。これは、画面の小さなスマホでは難しい操作ですよね。
また、Excelを使えば学習計画や成績管理も簡単。自分の学習状況をデータで「見える化」することで、やるべきことが明確になり、無駄なく勉強を進められます。
理由2:映像や音声で理解が深まる
理科の実験や社会の歴史的な出来事など、教科書や参考書の文章だけではイメージしにくい内容も、パソコンを使えば一瞬で解決します。YouTubeなどの動画サイトには、分かりやすい解説動画が豊富にあります。
例えば、理科の「天体の動き」は、動画で太陽や星の動きを見れば直感的に理解できます。視覚と聴覚の両方から情報をインプットすることで、記憶に定着しやすくなるのです。これは、紙の学習だけでは得られない大きなメリットと言えるでしょう。
理由3:情報収集・整理能力が身につく
調べ学習やレポート作成は、パソコンの得意分野です。インターネット上には膨大な情報がありますが、その中から「正しい情報」を見つけ出し、「自分なりに解釈してまとめる」という作業は、思考力を鍛える絶好のトレーニングになります。
このスキルは、高校での探求学習や大学での論文作成、社会に出てからの企画書作りなど、あらゆる場面で求められる重要な能力です。
理由4:高校・大学・社会で必須のスキルになる
今の時代、Word、Excel、PowerPointといったOfficeアプリは、使えて当たり前の基本スキルです。中学生のうちからレポート作成やデータ集計、プレゼン資料作りに慣れておけば、高校や大学の授業で困ることはありません。
さらに、タイピングスキルも重要です。キーボードを見ずに素早く正確に入力できる「タッチタイピング」を習得すれば、文章作成のスピードが飛躍的に向上し、勉強や課題にかかる時間を大幅に短縮できます。
【基本編】中学生がパソコンで始める勉強法5ステップ
では、具体的にパソコンをどう使って勉強すればいいのでしょうか?ここでは、明日からすぐに始められる基本的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:学習計画を立てる(Excel活用)
まずは、勉強の全体像を把握するための計画を立てましょう。ここでおすすめなのがExcelの「学習スケジュール表」テンプレートです。
曜日ごと、時間ごとに「どの教科を」「何をやるか」を具体的に書き込めます。定期テストや受験から逆算して計画を立てることで、やるべきことが明確になります。
- ポイント:計画通りに進んだ項目は色を塗るなどして、達成感を味わえるように工夫すると継続しやすくなります。
- おすすめテンプレート:Microsoftが提供している無料の「学習スケジュール表」は、シンプルで使いやすく、受験勉強にも最適です。
ステップ2:オンライン学習サービスでインプット
計画を立てたら、次はインプットです。特に、苦手な単元や理解が曖昧な部分は、オンライン学習サービスの動画解説を活用しましょう。
プロの講師による授業は非常に分かりやすく、何度も繰り返し視聴できるのが魅力です。一時停止してノートを取ったり、1.5倍速で復習したりと、自分のペースで学習を進められます。具体的なおすすめサービスは、後の章で詳しく紹介しますね。
ステップ3:調べ学習&レポート作成(Word活用)
インプットした知識を定着させるには、アウトプットが不可欠です。社会や理科の調べ学習で、特定のテーマについて深く掘り下げ、Wordを使ってレポートにまとめてみましょう。
インターネットで情報を集め、図や写真を挿入し、自分の言葉で考察を加える。この一連の作業は、知識の定着だけでなく、論理的思考力や表現力を養うのに非常に効果的です。
- おすすめテンプレート:Microsoftの「論文、レポートテンプレート」を使えば、体裁の整ったレポートが簡単につくれます。

ステップ4:オリジナル単語帳を作る(Word/Excel活用)
英単語や歴史の年号、理科の用語など、暗記項目はオリジナル単語帳で効率的に覚えましょう。WordやExcelのテンプレートを使えば、自分だけの単語帳が簡単に作成できます。
パソコンで作成するメリットは、編集や複製が簡単なこと。苦手な単語だけを集めた「弱点克服単語帳」を作ったり、友達と問題を出し合ったりと、様々な活用が可能です。
- おすすめテンプレート:Microsoftの「単語帳 (英語・学習)テンプレート」は、PC入力でも手書きでも使える便利なフォーマットです。
ステップ5:タイピングスキルを磨く
これら全ての作業の効率を上げるために、タイピング練習も並行して行いましょう。最初は面倒に感じるかもしれませんが、タッチタイピングができるようになれば、一生の財産になります。
無料のタイピング練習アプリやサイトがたくさんあるので、ゲーム感覚で毎日少しずつ取り組むのがおすすめです。目標は、キーボードを見ずに、友達とチャットするような感覚でスラスラ入力できるようになることです。
パソコンで勉強!中学生におすすめの無料サービス5選
ここからは、中学生のパソコン勉強に本当に役立つ無料オンライン学習サービスを5つ紹介します。「無料だから」と侮ってはいけません。有料サービスに負けない、ハイクオリティなコンテンツばかりですよ!
1. 19ch(塾チャンネル):圧倒的網羅性のYouTube授業
「とある男が授業をしてみた」でも有名な教育YouTuber・葉一(はいち)さんが運営するサイトです。小学校から高校までの授業動画がなんと2,000本以上も公開されており、その全てが無料。中学生向けの5教科は、学年別・単元別に整理されていて、教科書に合わせて学習を進められます。
レビュー
葉一さんの授業の最大の魅力は、その「分かりやすさ」と「親しみやすさ」です。まるで隣で優しいお兄さんが教えてくれているような感覚で、数学の難しい公式や、古文のややこしい助動詞もスッと頭に入ってきます。ホワイトボードを使ったシンプルな授業スタイルなので、要点が非常に分かりやすいです。動画に対応した無料のテキスト(PDF)をダウンロードして印刷すれば、ノートを取る手間も省け、効率的に学習できます。「学校の授業でつまずいてしまった」「塾には行ってないけど、しっかり勉強したい」という中学生には、まさに救世主のようなサービスです。
- 対応教科:数学・理科・英語・国語(文法・古文)・社会
- おすすめポイント:動画本数が圧倒的に多く、高校受験対策専用の動画も充実している。
- こんな人におすすめ:自分のペースで基礎からしっかり学び直したい人、塾代わりになる無料サービスを探している人。
2. Try IT(トライイット):”トライ品質”の映像授業
「家庭教師のトライ」が提供する無料の映像授業サービスです。さすが業界最大手だけあって、授業のクオリティは折り紙付き。中学・高校の主要教科を網羅し、4,000本以上の授業動画がすべて無料(※要無料会員登録)で見放題です。
レビュー
Try ITの授業は1本約15分。集中力が続きやすい絶妙な時間設定です。個性豊かな実力派講師陣が、アニメーションや図を駆使して視覚的に分かりやすく解説してくれます。特に理科や社会は、ビジュアル的な解説が理解を大いに助けてくれるでしょう。また、「専用テキスト(別売)」があるのもポイント。動画を見ながらテキストに書き込む形式で学習すれば、知識の定着率が格段にアップします。キーワードで動画を検索できる機能や、学習の進捗が記録される機能など、使いやすさも抜群。まるで自分専用のオンライン塾のようです。
- 対応教科:5教科
- おすすめポイント:プロ講師による高品質な授業、1本15分で集中しやすい、使いやすい学習システム。
- こんな人におすすめ:質の高い授業で効率よく学びたい人、定期テスト対策から高校受験まで幅広く活用したい人。
3. NPO法人eboard(イーボード):学びを諦めないためのICT教材
「すべての子どもたちに学ぶ機会を」という想いから生まれた、NPO法人が運営する無料のICT教材です。パソコンやタブレットで利用できる映像授業とデジタルドリルがセットになっており、自分のペースで着実に学習を進めることができます。
レビュー
eboardの動画は1本あたり7〜8分と非常にコンパクト。親しみやすい口調で丁寧に解説が進むので、勉強に苦手意識がある子でも取り組みやすいのが特徴です。動画を見た後すぐに連携するデジタルドリルに挑戦できるため、「わかる」と「できる」が直結しやすい学習サイクルが作れます。学校に行けていない不登校の生徒さんにとっても、教科書に沿った内容を自宅で学べる心強い味方になるでしょう。勉強の進捗が記録されるので、保護者の方がお子さんの頑張りを把握しやすいのも嬉しいポイントです。
- 対応教科:5教科
- おすすめポイント:映像授業とドリルが連動している、親しみやすい解説、不登校支援にも活用できる。
- こんな人におすすめ:勉強が苦手な人、基礎から少しずつステップアップしたい人、自分のペースで学びたい人。
4. スクールTV:教科書に完全対応!
株式会社イー・ラーニング研究所が提供する無料学習動画サービスです。最大の特徴は、小中学生の教科書に対応していること。自分の使っている教科書の目次から動画を探せるので、「学校の授業の予習・復習」に最適です。
レビュー
「授業で聞き逃した部分をもう一度確認したい」「明日の授業の予習をしておきたい」という時に、ピンポイントで必要な動画にたどり着ける利便性は非常に高いです。授業動画はすべて無料(※要会員登録)で、さらに理解を深めたい場合は、動画と連動したドリル(有料)に取り組むことも可能。まずは無料で試してみて、自分に合っていると感じたら有料プランを検討するという使い方ができるのが良いですね。
- 対応教科:5教科
- おすすめポイント:教科書の目次から動画を探せる、予習・復習に便利。
- こんな人におすすめ:学校の授業内容を確実に理解したい人。
5. Asuka Academy:世界レベルの学びを体験
少し背伸びして、知的好奇心を満たしたい中学生におすすめなのが「Asuka Academy」です。MITやイェール大学など、海外のトップ大学で行われている講義を、日本語字幕付きで無料視聴できます。
レビュー
もちろん、大学レベルの講義は難しいものも多いですが、「経済学」「パラドックス思考」など、中学生でも知的好奇心をくすぐられるようなテーマがたくさんあります。また、中高生向けのサイエンス動画や英語ニュースといった教材も充実。英語のリスニング力を鍛えたり、海外の文化に触れたりする良い機会になります。「勉強」という枠を超えて、自分の興味や関心を広げ、将来の夢を見つけるきっかけになるかもしれません。
- 対応分野:サイエンス、経済学、英語ニュースなど多岐にわたる
- おすすめポイント:海外トップレベルの講義に触れられる、知的好奇心を満たせる。
- こんな人におすすめ:普通の勉強に物足りなさを感じている人、海外に興味がある人、将来の夢を探している人。
効率UP!中学生向けパソコン勉強アプリ3選
続いて、学習効率をさらに高めてくれるパソコン用の「勉強アプリ」を紹介します。Webサービスと組み合わせて使うことで、効果は倍増しますよ。
1. マナビミライ:暗記学習の決定版
「マナビミライ」は、理科や社会、英単語などの暗記に特化した学習アプリです。シリーズ累計50万ダウンロードを突破している人気アプリで、すべての機能が無料で利用できます。
レビュー
このアプリのすごいところは、間違えた問題や苦手な問題を自動で記録し、繰り返し出題してくれる機能がある点です。自分で苦手な部分を意識しなくても、アプリが効率的な復習をサポートしてくれます。まさに「自分専用の家庭教師」のよう。一問一答形式でサクサク進められるので、勉強の合間の隙間時間や、ちょっとした気分転換にも最適です。作成した問題シートは印刷も可能なので、テスト直前に紙で最終確認することもできます。
- 特徴:暗記に特化、苦手問題を自動で繰り返し出題、印刷可能。
- こんな人におすすめ:暗記科目が苦手な人、効率的に弱点を克服したい人、隙間時間を有効活用したい人。
2. Microsoft Office アプリ:学習の基本ツール
Word、Excel、PowerPointは、単なる「アプリ」というよりも、パソコン勉強の基盤となる「必須ツール」です。先ほども紹介しましたが、改めてその活用法を整理します。
レビュー
Wordは「思考を整理し、表現する力」、Excelは「情報を分析し、管理する力」、PowerPointは「要点をまとめ、伝える力」を養います。これらのスキルは、受験勉強はもちろん、その後の人生においてもあらゆる場面で役立ちます。中学生のうちから、無料のテンプレートなどを活用して、楽しみながらこれらのアプリに触れておくことを強くおすすめします。最初は難しくても、ショートカットキーなどを覚えていくうちに、作業効率がどんどん上がっていくのを実感できるはずです。
- Word:レポート作成、オリジナル問題集作成
- Excel:学習計画表、成績管理、データ分析
- PowerPoint:調べ学習の発表資料作成、暗記カード作成
3. タイピング・マスター:ゲーム感覚でスキルアップ
パソコン勉強の効率を左右する「タイピングスキル」を、楽しみながら向上させるためのアプリです。特に子供向けに作られており、ゲーム感覚で練習できるのが特徴です。
レビュー
正しい指の位置(ホームポジション)から丁寧に教えてくれるので、初心者でも安心して始められます。単調になりがちなタイピング練習も、ゲーム要素があれば飽きずに続けられますよね。目標は、キーボードを見ずに入力できる「タッチタイピング」の習得です。これができるようになると、思考のスピードで文字が入力できるようになり、レポート作成やノートまとめの時間が劇的に短縮されます。毎日10分でも良いので、コツコツ続けてみましょう。
- 特徴:ゲーム感覚で練習できる、初心者向け。
- こんな人におすすめ:タイピングに自信がない人、楽しみながらスキルを身につけたい人。

パソコンでの勉強を成功させるための注意点とコツ
便利なパソコンですが、使い方を間違えると逆効果になってしまうことも。ここでは、パソコン勉強を成功させるための3つの重要なポイントをお伝えします。
1. 誘惑に負けない!集中力を維持する工夫
パソコンの一番の敵は、YouTubeの関連動画やゲーム、SNSなどの「誘惑」です。勉強を始めたはずが、いつの間にか関係ない動画を見てしまっていた…なんて経験、ありませんか?
対策として、勉強専用のブラウザユーザーを作成したり、特定のサイトへのアクセスを制限する機能拡張(アドオン)を活用するのがおすすめです。また、「25分勉強して5分休憩する」といったポモドーロ・テクニックを取り入れ、時間を区切って集中するのも効果的です。
2. 目や身体の健康を守るための休憩術
長時間同じ姿勢で画面を見続けると、目が疲れたり、肩が凝ったりします。健康を害してしまっては元も子もありません。
最低でも1時間に1回は立ち上がってストレッチをしたり、遠くの景色を眺めたりして目を休ませましょう。画面の明るさを調整したり、ブルーライトカットのメガネを使ったりするのも有効です。正しい姿勢を保つことも忘れないでくださいね。
3. 親子で決めたい!パソコン利用のルール作り
特に自分専用のパソコンがない場合は、保護者の方とのルール作りが大切です。「何時から何時まで使うのか」「勉強以外には使わない」など、最初にきちんと話し合っておきましょう。
保護者の方も、フィルタリングソフトを活用するなどして、お子さんが安全にインターネットを利用できる環境を整えてあげることが重要です。お互いに信頼し合い、気持ちよくパソコン勉強に取り組める環境を作りましょう。
【応用編】将来に役立つ!パソコンスキルアップ術
基本の勉強法に慣れてきたら、さらに一歩進んだスキルアップに挑戦してみませんか?ここで身につけるスキルは、間違いなくあなたの将来の武器になります。
プログラミングに挑戦してみよう(MakeCode)
Microsoftが提供する「MakeCode」は、ブラウザ上で簡単にプログラミングを学べる無料のプラットフォームです。ブロックを組み合わせるビジュアルコーディングなので、初心者でも直感的にプログラミングの基礎を体験できます。論理的思考力や問題解決能力を養うのに最適なツールです。
覚えておきたいキーボードショートカット術
マウスを使わずにキーボードだけでパソコンを操作する「ショートカットキー」を覚えると、作業効率が劇的に向上します。最初は少し戸惑うかもしれませんが、意識して使っているうちに自然と指が覚えていきます。
| ショートカットキー | 操作内容 |
|---|---|
| [Ctrl] + [C] | 選択した項目をコピーする |
| [Ctrl] + [V] | コピーした項目を貼り付ける |
| [Ctrl] + [X] | 選択した項目を切り取る |
| [Ctrl] + [Z] | 操作を元に戻す |
| [Ctrl] + [S] | ファイルを上書き保存する |
| [Ctrl] + [A] | すべての項目を選択する |
まずはこの6つから覚えてみてください。これだけでも、作業スピードが大きく変わるはずです。
プレゼン資料作成の基本(PowerPoint)
調べ学習でまとめた内容を、PowerPointを使って発表資料にしてみましょう。「どうすれば相手に分かりやすく伝わるか」を考えることは、最高のプレゼンテーションスキルのトレーニングになります。写真やグラフを効果的に使い、自分だけの発表資料を作成してみてください。文化祭の発表などでも大活躍しますよ。
中学生のパソコンでの勉強に関するQ&A
最後に、中学生や保護者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
結論から言うと、今回紹介したような勉強目的であれば、高性能なパソコンは必要ありません。インターネットに繋がり、Officeアプリがスムーズに動作する、ごく標準的なスペックのノートパソコンで十分です。動画編集やオンラインゲームもしたい場合は、少しスペックの高いものが必要になりますが、まずは学習用途に絞って選ぶのが良いでしょう。
一番の違いは、「キーボードとマウスによる操作性」と「マルチタスク性能」です。長文のレポート作成や複雑なデータ入力は、キーボードがあるパソコンの方が圧倒的に効率的です。また、複数のウィンドウを開いて情報を比較しながら作業できるのもパソコンの強みです。インプット(動画視聴など)はタブレット、アウトプット(レポート作成など)はパソコン、と使い分けるのも賢い方法です。
ただ「欲しい」と伝えるのではなく、「なぜ必要なのか」「どうやって勉強に活かすのか」を具体的にプレゼンすることが大切です。この記事で紹介したような無料サービスやテンプレートを見せながら、「こういう風に学習計画を立てて、苦手な英語を克服したいんだ」と、あなたの本気度と具体的な活用計画を伝えましょう。パソコン利用のルールを自分から提案するのも、保護者の方の安心につながり、説得力が増すはずです。
まとめ:パソコンを最強の勉強ツールにしよう!
今回は、中学生がパソコンを使って勉強する方法について、網羅的に解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- パソコンでの勉強は、効率アップや深い理解につながるだけでなく、将来必須となるデジタルスキルが身につく。
- まずは「計画→インプット→アウトプット→スキルアップ」の5ステップを実践してみよう。
- 「19ch」や「Try IT」など、無料で高品質な学習サービスがたくさんあるので、積極的に活用しよう。
- 暗記には「マナビミライ」、レポート作成には「Officeアプリ」など、目的に合わせてツールを使い分けるのが効率UPの鍵。
- 誘惑に負けないルール作りや、健康への配慮も忘れずに。
パソコンは、ゲームや動画視聴のための道具だけではありません。あなたの使い方次第で、成績を飛躍的に向上させ、将来の可能性を広げる「最強の勉強ツール」になります。
この記事を読んで「やってみよう!」と思ったあなたは、もうすでにライバルより一歩リードしています。まずは、今回紹介した無料のサービスの中から、気になるものを一つ試すことから始めてみませんか?
あなたの挑戦を、心から応援しています!