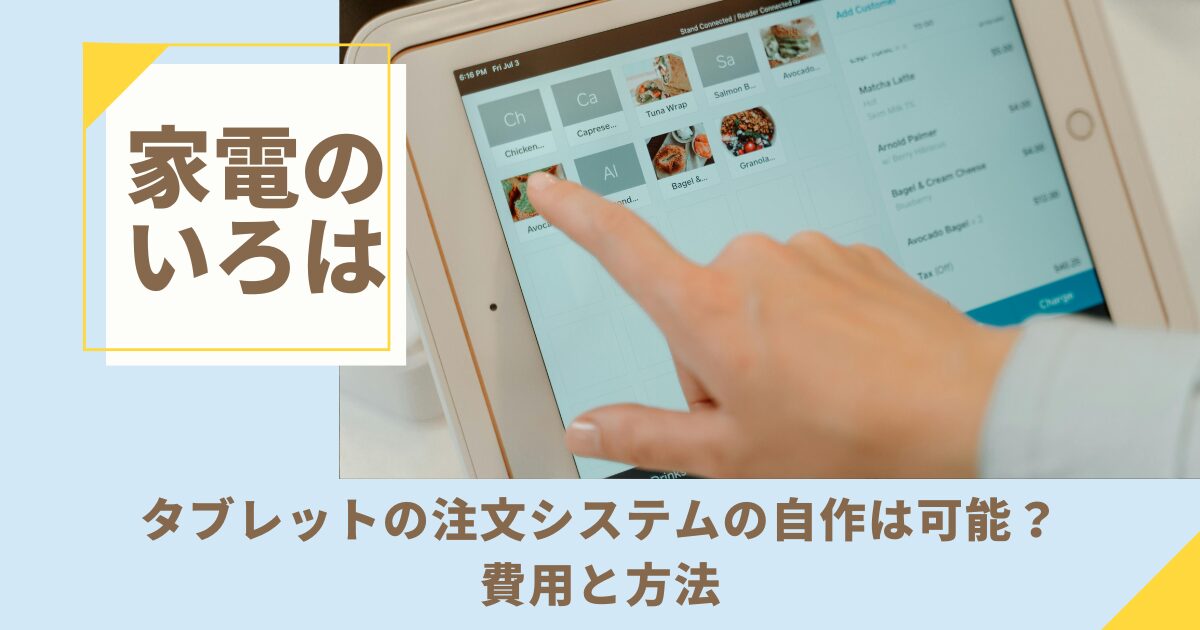「飲食店の人件費を削減したい…」
「もっと自由にカスタマイズできる注文システムが欲しい…」
「初期費用を抑えてセルフオーダーを導入したい…」
このような悩みを抱えている飲食店経営者や店舗オーナーの方、多いのではないでしょうか?
近年、多くの飲食店で導入が進むタブレット注文システム(セルフオーダーシステム)。業務効率化や人手不足解消の切り札として注目されていますが、導入コストがネックになっているケースも少なくありません。
そんな中、「タブレットの注文システムは自作できないだろうか?」と考えたことはありませんか?
この記事では、そんなあなたの疑問に徹底的に答えます。結論から言うと、タブレット注文システムの自作は可能です。
しかし、そこにはメリットだけでなく、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。この記事では、プログラミング初心者の方でも理解できるよう、以下の点をどこよりも詳しく、網羅的に解説していきます。
- タブレット注文システムを自作するメリット・デメリット
- 自作と既製品の徹底比較
- 具体的な自作方法5ステップ
- 無料でシステムを構築する方法
- 自作におすすめの高品質な中古タブレット情報
この記事を最後まで読めば、あなたのお店に最適なオーダーシステム導入の道筋が明確になり、コストを抑えながら業務効率を劇的に改善する第一歩を踏み出せるはずです。さあ、一緒に見ていきましょう!
タブレット注文システムは自作できる?【結論】
まず、この記事の核心である「タブレット注文システムは自作できるのか?」という問いにお答えします。
結論として、タブレット注文システムの自作は十分に可能です。プログラミングの知識や開発スキルがあれば、お店の運用に合わせたオリジナルのシステムを構築できます。実際に、個人経営のカフェや小規模な居酒屋などで、独自のシステムを開発・運用しているケースも存在します。
しかし、「可能であること」と「誰にでも簡単にできること」はイコールではありません。自作には多くのメリットがある一方で、相応の技術力、時間、そして乗り越えるべきハードルがあることも事実です。
自作の現実的なハードルとは?
自作を検討する上で、まず理解しておくべきは、求められる技術レベルです。最低限、以下のような知識やスキルが必要になります。
- フロントエンド開発:お客様が直接触れるメニュー画面や注文ボタンなどを作成する技術(HTML, CSS, JavaScriptなど)
- バックエンド開発:注文データを受け取り、データベースに保存したり、キッチンに指示を出したりするサーバー側の処理を担う技術(Python, PHP, Ruby, Node.jsなど)
- データベース設計・管理:メニュー情報、注文履歴、顧客情報などを保存・管理するためのデータベースを設計・運用する知識(MySQL, PostgreSQLなど)
- ネットワーク・インフラ構築:タブレット、サーバー、キッチンプリンターなどを連携させるためのネットワーク環境を構築する知識
これらの技術をゼロから学ぶのは、決して簡単なことではありません。もしあなたがプログラミング未経験者であれば、学習だけで数ヶ月から1年以上の期間が必要になる可能性も覚悟しておく必要があります。

「なんだか難しそう…」と感じたかもしれませんね。でも、ご安心ください!この記事では、こうした技術的な課題を乗り越えるためのヒントや、自作が難しい場合の代替案もしっかりとご紹介しますので、まずは自作の可能性を探っていきましょう!
自作が向いている人・お店の特徴
では、どのような人やお店が自作に向いているのでしょうか?一般的に、以下のようなケースが考えられます。
- プログラミング経験がある、または学習意欲が高い人
- お店のオペレーションが特殊で、既製品では対応できない独自の機能が必要なお店
- 初期費用を極限まで抑えたい個人経営の小規模店舗
- 時間をかけてでも、理想のシステムを追求したいという情熱がある人
- システムの保守・運用を自分で行える、または信頼できる技術者がいる場合
もしこれらのいずれかに当てはまるなら、タブレット注文システムの自作に挑戦する価値は十分にあります。次の章からは、自作の具体的なメリット・デメリットを詳しく見ていき、あなたが本当に自作に踏み出すべきかを判断する材料を提供していきます。
メリット満載!セルフオーダーシステム自作の魅力
時間や技術的なハードルがあるにもかかわらず、なぜ「自作」という選択肢が魅力的に映るのでしょうか?それは、既製品にはない、自作ならではの大きなメリットがあるからです。ここでは、セルフオーダーシステムを自作することで得られる主な魅力を4つのポイントに絞って詳しく解説します。
1. 圧倒的なコスト削減!月額費用からの解放
自作の最大のメリットは、何と言ってもコストを大幅に削減できる点です。既製品のセルフオーダーシステムを導入する場合、一般的に以下のような費用が発生します。
- 初期導入費用:数十万円〜数百万円
- 月額利用料:数万円〜十数万円
- 周辺機器の購入・レンタル費用:タブレット、プリンター、アクセスポイントなど
特に、毎月発生する月額利用料は、長期的に見ると大きな負担となります。一方、自作であれば、これらの費用を劇的に抑えることが可能です。必要なコストは、基本的にタブレットなどのハードウェア購入費用と、サーバーを運用する場合のレンタルサーバー代(月額数百円〜数千円程度)のみ。月額費用がほぼゼロになるのは、経営者にとって非常に大きな魅力と言えるでしょう。
2. 理想を形に!完全オリジナルのカスタマイズ性
「うちの店だけの特別メニューを、もっと魅力的に見せたい」「お客様がワクワクするような注文体験を提供したい」そんな思いはありませんか?
自作システムのもう一つの大きな魅力は、デザインや機能を思い通りにカスタマイズできることです。既製品の場合、提供されているテンプレートや機能の範囲内でしかカスタマイズできませんが、自作なら制限は一切ありません。
- お店のブランドイメージに合わせたデザインのメニュー画面
- 「本日のおすすめ」や「SNS映えメニュー」を強調する独自のレイアウト
- アレルギー情報の詳細表示や、辛さ・トッピングの細かい選択機能
- 特定の顧客層(例:常連客、観光客)に合わせたメニューの出し分け
- ゲーム性を取り入れた注文システム(例:ガチャで割引クーポン)
このように、お店の個性やコンセプトを最大限に反映させた、世界に一つだけの注文システムを作り上げることができます。これは、他店との差別化を図り、顧客満足度を向上させる強力な武器となります。
3. 外部サービスとの自由な連携
既製品のシステムでは、連携できるPOSレジや決済サービスが限定されていることが少なくありません。しかし、自作であれば、API(Application Programming Interface)などを活用して、様々な外部サービスと自由に連携させることが可能です。
例えば、以下のような連携が考えられます。
- 既に使用している会計ソフトやPOSレジとのデータ連携
- 複数のキャッシュレス決済サービスとの連携
- 顧客管理システム(CRM)と連携し、注文履歴に基づいたクーポンを発行
- 在庫管理システムと連携し、品切れメニューをリアルタイムで非表示に
これにより、店舗全体の業務フローをシームレスに繋ぎ、さらなる効率化を実現できます。
4. エンジニアとしてのスキルアップ
もしあなたが経営者自身、あるいは店舗スタッフが開発に携わるのであれば、システムを自作する過程そのものが、貴重な学びとスキルアップの機会になります。
Web開発の知識やプログラミングスキルは、今後の店舗運営においても様々な場面で役立つはずです。例えば、お店のウェブサイトを改修したり、新たなWebサービスを立ち上げたりと、ビジネスの可能性を広げる力になるでしょう。困難な開発を乗り越えてシステムが完成した時の達成感は、何物にも代えがたい経験となります。

コスト削減やカスタマイズ性など、自作にはたくさんの夢がありますよね!でも、良いことばかりではありません。次の章では、現実的なデメリットもしっかりと見ていきましょう。
始める前に知るべき!システム自作のデメリットと注意点
前章で解説したように、タブレット注文システムの自作には大きな魅力があります。しかし、その裏には見過ごすことのできないデメリットや注意点が存在します。安易に自作に踏み切って「こんなはずではなかった…」と後悔しないためにも、ここで紹介する4つのリスクを必ず理解しておきましょう。
1. 膨大な開発時間と専門知識の壁
最も大きなデメリットは、システム完成までに膨大な時間と労力がかかることです。前述の通り、自作にはフロントエンド、バックエンド、データベース、インフラなど、多岐にわたる専門知識が不可欠です。
プログラミング経験者であっても、要件定義から設計、開発、テストまで含めると、シンプルなシステムでも数ヶ月単位の期間が必要になるでしょう。もし未経験者であれば、まずは学習からスタートする必要があるため、1年以上の長期プロジェクトになる可能性も十分にあります。
本業である店舗運営と並行して開発を進めるのは、想像以上に困難を極めます。「いつまで経っても完成しない」「開発に時間を取られすぎて本業がおろそかになる」といった事態に陥るリスクを十分に考慮する必要があります。
2. トラブルは自己責任!保守・運用の負担
システムは作って終わりではありません。むしろ、完成後の保守・運用こそが重要です。既製品であれば、提供会社がシステムのメンテナンスやアップデート、トラブル対応を行ってくれますが、自作の場合はそのすべてを自分で行わなければなりません。
- システム障害:「急に注文が通らなくなった」「データが消えてしまった」といったトラブルが発生した場合、営業を止め、原因を特定し、自力で復旧させる必要があります。
- セキュリティ対策:悪意のある第三者からの攻撃や情報漏洩を防ぐため、常に最新のセキュリティ対策を講じる必要があります。クレジットカード情報などを扱う場合は、特に高度な知識が求められます。
- OS・ソフトウェアのアップデート対応:タブレットのOSや、開発に使用したプログラミング言語、ライブラリなどがアップデートされた際に、システムが正常に動作しなくなることがあります。定期的なメンテナンスと改修が不可欠です。
営業中の突然のトラブルに対応できるスキルと体制がなければ、お客様に多大な迷惑をかけ、お店の信用を失うことにもなりかねません。

特にセキュリティは見落としがちなポイントです!お客様の個人情報や決済情報を扱うシステムを自作する場合、その責任はすべて自分にあるということを肝に銘じておきましょう。
3. 想定外のコストが発生する可能性
「自作=安い」と安易に考えるのは危険です。開発が難航し、外部のエンジニアに協力を依頼することになれば、結果的に既製品を導入するよりも高額になるケースもあります。
また、開発に必要なパソコンのスペックアップ費用、学習のための書籍代やオンライン講座の受講料、様々なツールやサービスの利用料など、細かな出費が積み重なることも忘れてはいけません。ハードウェア費用とサーバー代以外にも、見えないコストが発生する可能性を考慮しておきましょう。
4. 機能不足や使いにくさの問題
時間と労力をかけて開発したにもかかわらず、「結局、機能が足りなかった」「スタッフやお客様にとって使いにくいシステムになってしまった」というのも、よくある失敗例です。
プロが開発した既製品は、長年のノウハウが蓄積されており、飲食店のオペレーションに最適化されたUI/UX(使いやすさ)が設計されています。自作の場合、開発者の視点だけで作ってしまい、実際に使う人の立場を考えた設計が疎かになりがちです。結果として、業務効率が上がるどころか、逆に下がってしまうという本末転倒な事態も起こり得ます。
これらのデメリットを理解した上で、それでも自作に挑戦したいという強い意志があるかどうかが、成功の分かれ道となります。次の章では、改めて「自作」と「既製品」を客観的に比較し、あなたにとって最適な選択肢はどちらなのかを考えていきましょう。
【徹底比較】自作 vs 既製品 どっちを選ぶべき?
ここまで、タブレット注文システムを自作するメリットとデメリットを詳しく見てきました。では、結局のところ、「自作」と「既製品の導入」、どちらがあなたのお店にとって最適な選択なのでしょうか?
この章では、それぞれの特徴を比較表にまとめ、どのようなお店にどちらの選択肢が向いているのかを具体的に解説します。この比較を通じて、あなたの進むべき道がより明確になるはずです。
自作と既製品の比較一覧表
まずは、重要な項目ごとに自作と既製品を比較してみましょう。
| 項目 | 自作システム | 既製品システム |
|---|---|---|
| 初期費用 | 安い(ハードウェア代が中心) | 高い(数十万〜数百万円) |
| 月額費用 | ほぼゼロ(サーバー代など) | かかる(数万〜十数万円) |
| カスタマイズ性 | 非常に高い(自由自在) | 低い(提供範囲内) |
| 開発期間 | 非常に長い(数ヶ月〜1年以上) | 短い(契約後すぐ〜数週間) |
| 専門知識 | 必須(広範囲なITスキル) | 不要 |
| サポート体制 | なし(すべて自己責任) | あり(導入支援、トラブル対応) |
| 信頼性・安定性 | 開発者のスキルに依存 | 高い(プロが開発・運用) |
| セキュリティ | 自己で高度な対策が必要 | 高い(提供会社が保証) |
自作がおすすめな飲食店
上記の比較表を踏まえると、以下のような特徴を持つ飲食店には自作という選択肢が適していると言えます。
- とにかく初期投資とランニングコストを抑えたい個人経営の小規模店
- オーナーやスタッフにプログラミング経験者がいる
- お店のコンセプトが非常にユニークで、既製品では表現できない世界観をシステムに反映させたい
- 時間をかけてでも、自分たちの手で理想の店作りを追求したいという強い情熱がある
- システムにトラブルがあっても、営業に大きな支障が出ないオペレーションが組める
自作は、ハイリスク・ハイリターンな選択肢です。成功すれば、コストを抑えつつ他店にはない強力な武器を手に入れることができます。しかし、そのためには相応の覚悟とスキルが求められます。
既製品の導入がおすすめな飲食店
一方で、以下のような飲食店には、既製品の導入を強くおすすめします。
- ITやプログラミングに関する専門知識がない、または時間をかけられない
- 複数店舗を展開しており、安定したシステム運用と手厚いサポートを重視する
- コストよりも、確実な業務効率化とスピーディーな導入を優先したい
- POSレジや勤怠管理など、既存のシステムと確実に連携させたい
- システムのトラブルで営業が止まるリスクを絶対に避けたい
多くの飲食店にとっては、信頼と実績のある既製品システムを導入する方が、結果的に時間と労力を節約でき、本業である料理や接客に集中できるため、賢明な判断と言えるでしょう。近年は、比較的安価で導入できるクラウド型のサービスも増えています。

いかがでしたか?ご自身のお店の状況と照らし合わせて、どちらが向いているか見えてきましたか?もし「それでも自作に挑戦したい!」という方は、次の章からいよいよ具体的な自作方法を解説していきますので、ぜひご覧ください!
セルフオーダーシステム自作の具体的な方法5ステップ
「リスクは理解した。それでも、自分だけの注文システムを作ってみたい!」そんな熱意あるあなたのために、ここからはセルフオーダーシステムを自作するための具体的な手順を5つのステップに分けて、できるだけ分かりやすく解説していきます。このロードマップに沿って進めれば、ゴールまでの道のりが明確になるはずです。
Step 1:最重要!システムの要件定義(何を作るか決める)
開発を始める前に、まず「どんなシステムを作りたいのか」を明確にする「要件定義」という作業が最も重要です。ここが曖昧なままだと、開発途中で方向性がブレたり、完成したものが使い物にならなかったりする原因になります。
以下の項目を紙やドキュメントに書き出してみましょう。
- 【必須機能】これだけは絶対に外せない機能は何か?
- 例:カテゴリー別メニュー表示、注文機能、注文内容のキッチンへの送信機能
- 【追加機能】あったら嬉しい機能は何か?
- 例:多言語対応(英語、中国語など)、アレルギー表示、店員呼び出し機能、お会計機能
- 【画面設計】お客様が使う画面、スタッフが使う画面はそれぞれどんなものか?
- 手書きのラフスケッチで構いません。画面にどんな情報をどのように表示するかイメージを具体化します。
- 【連携】POSレジやプリンターなど、どの機器と連携させるか?
- 連携させたい機器の仕様(APIの有無など)も確認しておきましょう。
- 【対象ユーザー】誰が、どの端末で使うのか?
- 例:お客様が各テーブルのiPadで注文する、スタッフがハンディとしてiPhoneを使う
この段階でできるだけ詳細に決めておくことが、後の手戻りを防ぎ、開発をスムーズに進めるための鍵となります。
Step 2:必要な機材・ツールの準備
要件が決まったら、次は開発と運用に必要なモノを揃えます。大きく分けて「ハードウェア」「ソフトウェア」の2つが必要です。
ハードウェアの準備
- タブレット端末:お客様が注文に使うメインの機器です。iPadやAndroidタブレットが一般的です。
- サーバー:システム本体を動かすためのコンピューター。自前で用意する(オンプレミス)か、レンタルサーバーやクラウドサービス(AWS, GCPなど)を利用するのが一般的です。
- キッチンプリンター:キッチンに注文内容を印刷するための専用プリンター。
- Wi-Fiルーター:タブレットやプリンターをネットワークに接続するための機器。店舗の広さや構造に合ったものを選びましょう。
- 開発用PC:プログラミングを行うためのパソコン。

タブレットを複数台揃えるとなると、かなりのコストになりますよね。ここでコストを抑えるためのとっておきの情報があります!
コストを賢く抑えたいなら、中古タブレットの活用が断然おすすめです。特に、伊藤忠グループが運営する中古スマホ・タブレットのECサイト「にこスマ」は、品質と保証の面で非常に信頼できます。
「にこスマ」をおすすめする理由は以下の通りです。
- 高品質な端末のみを厳選:画面や本体に割れ・欠けがなく、25項目以上の機能検査をクリアした端末だけを販売しています。中古でも安心して使えます。
- キャリアを問わないSIMフリー:どの通信キャリアでも利用可能なので、柔軟なネットワーク構築ができます。
- 安心の1年間無料返品交換保証:万が一の初期不良にも対応してくれるので、中古品に不安がある方でも安心です。
自作システムの初期費用を大幅に削減できる「にこスマ」で、高品質なタブレットをお得に手に入れてみてはいかがでしょうか?公式サイトで豊富な品揃えをぜひチェックしてみてください。
ソフトウェア・開発環境の準備
- テキストエディタ:プログラムを書くためのソフト(例:Visual Studio Code)。
- プログラミング言語・フレームワーク:システムの要件に合わせて選びます。Web系でよく使われるのは、フロントエンドでReactやVue.js、バックエンドでPython(Django), PHP(Laravel), Node.js(Express)などです。
- データベース管理システム:MySQLやPostgreSQLなどが一般的です。
- バージョン管理システム:Git。ソースコードの変更履歴を管理するために必須です。
Step 3:データベースの設計と構築
次に、システムの土台となるデータベースを設計します。「メニュー情報」「注文情報」「座席情報」など、システムで扱うデータをどのように整理して保存するかを決める工程です。
具体的には、「テーブル」と呼ばれる表を作成し、それぞれのテーブルにどのような項目(例:メニューテーブルなら「商品ID」「商品名」「価格」「カテゴリー」など)を持たせるかを定義していきます。ここでしっかりとした設計ができていないと、後から機能を追加するのが難しくなったり、システムの動作が遅くなったりする原因になります。
Step 4:プログラミング(開発)
いよいよ、設計図をもとに実際にプログラムを書いていく、開発のメイン工程です。大きく「フロントエンド」と「バックエンド」に分かれます。
- フロントエンド開発:お客様が直接触れるメニュー画面を作成します。Step1で描いた画面設計図をもとに、見やすく、直感的に操作できるデザインをHTML, CSS, JavaScriptなどを使って実装します。
- バックエンド開発:フロントエンドからのリクエスト(注文など)を受け取り、データベースを操作したり、キッチンプリンターに印刷指示を送ったりといった、目に見えない部分の処理を実装します。
この工程が最も時間がかかり、専門的な知識が求められる部分です。一つ一つの機能を丁寧に作り上げていきましょう。
Step 5:テストと店舗への導入
システムが一通り完成したら、すぐに本番で使うのではなく、必ず「テスト」を行います。
- 単体テスト:個々の機能(例:注文ボタンを押す)が正しく動くかを確認します。
- 結合テスト:複数の機能を組み合わせたとき(例:注文してからキッチンに印刷されるまで)に、意図した通りに連携するかを確認します。
- 総合テスト:実際の店舗と同じ環境で、スタッフに操作してもらい、使い勝手や問題点がないかを徹底的に洗い出します。
ここで見つかった不具合をすべて修正し、誰もが安心して使える状態になったら、いよいよ店舗へ導入です。導入後も、使っていく中で出てきた改善点などを随時アップデートしていくことで、より良いシステムへと成長させていくことができます。
飲食店の注文システムの自作で成功するための重要ポイント
自作のロードマップが見えたところで、特に飲食店の注文システムを自作する上で、成功の確率をぐっと高めるための重要なポイントを3つご紹介します。技術的な話だけでなく、店舗運営の視点も踏まえた内容ですので、ぜひ参考にしてください。
1. UI/UX(使いやすさ)を最優先に設計する
どんなに高機能なシステムでも、お客様やスタッフにとって使いにくければ意味がありません。特に飲食店では、ITに不慣れな高齢のお客様から、アルバイトの高校生まで、幅広い層の人々がシステムを利用します。
UI/UXを設計する際は、以下の点を常に意識しましょう。
- 直感的な操作性:説明書を読まなくても、誰でも感覚的に操作できるか? ボタンの配置や文字の大きさは適切か?
- レスポンス速度:画面の切り替えや注文の反映はスムーズか? お客様を待たせないか?
- 誤操作の防止:注文確定前に確認画面を挟むなど、間違えて注文してしまうことを防ぐ工夫はされているか?
- 視認性:メニュー写真は美味しそうに見えるか? 文字は読みやすいか? お店の雰囲気に合ったデザインか?
開発中はつい機能の追加に目が行きがちですが、常に「使う人の視点」に立ち返ることが、本当に価値のあるシステムを作るための鍵となります。
2. キッチン・ホールとの連携を徹底的に考える
セルフオーダーシステムの目的は、単に注文を受けることだけではありません。キッチンやホールの業務をいかに効率化できるかが重要です。

例えば、キッチンへの指示の出し方は非常に重要です。ただ注文内容を印刷するだけでなく、調理の順番や提供タイミングまで考慮したシステム設計ができると、厨房の混乱を劇的に減らすことができますよ。
以下のような、現場のオペレーションを考慮した機能を盛り込みましょう。
- 注文の自動振り分け:ドリンクの注文はドリンクカウンターへ、フードの注文は調理場へ、と自動で印刷先を振り分ける機能。
- 調理状況の可視化:キッチン側で「調理中」「提供可能」などのステータスを管理し、ホールスタッフがリアルタイムで把握できる機能。
- 食べ放題・飲み放題の管理:残り時間の表示や、ラストオーダーの自動通知機能。
- テーブル管理:どのテーブルが空席か、食事中か、会計済みかなどを一覧で管理できるホールスタッフ用の画面。
開発を始める前に、キッチンやホールのスタッフにヒアリングを行い、現場の課題や要望をシステムに反映させることが成功への近道です。
3. スモールスタートで始めて徐々に拡張する
最初から完璧なシステムを目指そうとすると、開発期間が長引き、途中で挫折してしまうリスクが高まります。そこでおすすめなのが、「スモールスタート」という考え方です。
まずは、前章のStep1で考えた「必須機能」だけを実装した、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を開発することを目指しましょう。例えば、「メニューを表示して、注文内容をキッチンに送信する」というコア機能だけでも構いません。
この最小限のシステムを実際に店舗で運用してみて、お客様やスタッフからフィードバックをもらいます。そして、その意見を元に、本当に必要な機能から優先順位をつけて、少しずつ機能を追加・改善していくのです。
この方法には、以下のようなメリットがあります。
- 早期にシステムを導入でき、効果を実感しやすい。
- 開発のモチベーションを維持しやすい。
- 現場のニーズに基づいた、本当に役立つ機能だけを開発できる。
- 大きな失敗をするリスクを減らせる。
完璧を目指さず、まずは動くものを作る。そして、育てていく。このアプローチが、個人でのシステム開発を成功に導くための現実的な戦略と言えるでしょう。
【0円も可能?】無料で始めるセルフオーダーシステム構築術
「自作の魅力はわかったけど、やっぱり開発は難しそう…」「もっと手軽に、無料で試せる方法はないの?」と感じている方もいるかもしれません。実は、プログラミングをゴリゴリ書かなくても、既存のツールを組み合わせることで、無料でセルフオーダーシステムに近い仕組みを構築する方法も存在します。ここでは、その具体的なアイデアをいくつかご紹介します。
GoogleフォームとQRコードを活用する方法
最も手軽に始められるのが、Googleが提供する無料ツール「Googleフォーム」と「Googleスプレッドシート」を活用する方法です。
【構築手順】
- Googleフォームでメニュー作成:Googleフォームを使い、お店のメニューを質問項目として入力していきます。写真も掲載できるので、見やすいメニューが作成可能です。
- 回答をスプレッドシートに連携:フォームの回答(注文)が、自動的にGoogleスプレッドシートに記録されるように設定します。
- QRコードを生成:作成したGoogleフォームのURLからQRコードを生成します。無料で生成できるWebサービスがたくさんあります。
- テーブルに設置:生成したQRコードを印刷し、各テーブルに設置します。
【運用の流れ】
- お客様がテーブルのQRコードをスマートフォンで読み取る。
- 表示されたGoogleフォーム(メニュー)から注文したい商品を選択し、送信する。
- 注文内容がリアルタイムでGoogleスプレッドシートに記録される。
- キッチンやホールスタッフは、スプレッドシートが更新されたことを確認し、調理・提供を行う。

この方法ならプログラミング知識は一切不要です!スプレッドシートの通知機能を設定すれば、注文が入るたびにメールやチャットで知らせることも可能ですよ。
ただし、この方法にはデメリットもあります。リアルタイムでの注文管理が少し煩雑になったり、キッチンプリンターとの自動連携ができなかったりするため、注文数の多い大規模な店舗には向きません。しかし、小規模なカフェやバー、期間限定のイベントなどで「まずはお試しでセルフオーダーを導入してみたい」という場合には、非常に有効な手段です。
オープンソースソフトウェア(OSS)の活用
「オープンソースソフトウェア(OSS)」とは、ソースコードが一般公開されており、誰でも自由に利用、改変、再配布ができるソフトウェアのことです。世界中の開発者によって、様々なOSSが開発されており、中には飲食店向けの注文システムやPOSレジシステムも存在します。
【OSS活用のメリット】
- ソフトウェア自体のライセンス費用が無料。
- ソースコードを自分で改変できるため、カスタマイズ性が高い。
- 世界中の開発者が参加するコミュニティがあり、情報を得やすい場合がある。
【OSS活用の注意点】
- 導入や設定には、サーバーやデータベースなどの専門知識が必要。
- 公式なサポートは存在しないため、トラブルは自己解決が基本。
- 日本語に対応していない、日本の商習慣に合わない場合がある。
- セキュリティ対策は自分で行う必要がある。
代表的なOSSとしては「Odoo」や「Floreant POS」などがありますが、導入のハードルは決して低くありません。ある程度のITスキルを持つ方向けの選択肢と言えるでしょう。しかし、うまく活用できれば、無料で高機能なシステムを手に入れることができる可能性を秘めています。
POSレジアプリやモバイルオーダーシステム自作の可能性
タブレット注文システムと密接に関連するのが、「POSレジアプリ」や、テイクアウト・デリバリーで活用される「モバイルオーダーシステム」です。これらを自作することは、注文システム以上に店舗運営全体を効率化する可能性を秘めています。ここでは、これらのシステム自作の可能性とポイントについて掘り下げていきます。
POSレジアプリ自作のメリットと難易度
POS(Point of Sale)レジは、単なる会計機能だけでなく、売上分析や顧客管理、在庫管理など、店舗経営に不可欠なデータを集約する心臓部です。自作することで、以下のようなメリットが考えられます。
- 完全なデータ連携:自作の注文システムとシームレスに連携し、注文から会計までの流れを完全に自動化。
- 独自の売上分析:お店独自の視点(例:天気や時間帯と特定メニューの相関など)でデータを分析する機能を実装。
- ハードウェアの自由度:市販のレシートプリンターやキャッシュドロワー、決済端末など、好きな機器を自由に組み合わせられる。
しかし、POSレジアプリの自作は、注文システムの自作よりもさらに難易度が高くなります。特にお金が直接関わる部分であるため、計算ミスやデータの不整合は絶対に許されません。また、消費税の計算(軽減税率など)や、様々なキャッシュレス決済への対応、さらには法改正への追従など、考慮すべき点が非常に多く、高度な専門知識と継続的なメンテナンスが求められます。
個人でゼロから開発するのは非常にハードルが高いため、まずは「Airレジ」や「スマレジ」といった高機能な無料POSレジアプリを活用し、API連携で自作の注文システムと繋ぐ、というアプローチが現実的かもしれません。
モバイルオーダーシステム自作で商圏を拡大
モバイルオーダーシステムとは、お客様が自身のスマートフォンを使って、来店前に注文・決済を済ませておける仕組みのことです。テイクアウトやデリバリーの需要が高まる現代において、非常に重要なシステムとなっています。
自作のメリットは、やはりプラットフォーム手数料からの解放です。大手デリバリーサービスを利用すると、売上の30%〜40%という高額な手数料がかかることが一般的ですが、自社でシステムを構築すれば、そのコストを削減し、お客様に還元したり、利益率を高めたりすることが可能になります。

自社のファン(常連客)が多いお店ほど、自前のモバイルオーダーシステムを構築するメリットは大きいですね。お店独自のポイント制度などを導入すれば、顧客の囲い込みにも繋がります!
開発のポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- オンライン決済機能の実装:StripeやPAY.JPなどの決済代行サービスを利用するのが一般的です。
- 受け取り時間の指定機能:お客様が来店する時間を指定できるようにし、店舗側の調理計画をスムーズにする。
- 顧客への通知機能:「注文を受け付けました」「商品ができました」といった通知をメールやSMS、LINEなどで送信する仕組み。
- スマホに最適化されたUI/UX:小さな画面でもストレスなく操作できる、分かりやすいデザインが不可欠です。
モバイルオーダーシステムの自作も簡単ではありませんが、成功すれば、店内飲食だけでなく、テイクアウトという新たな収益の柱を確立し、商圏を大きく広げることができるでしょう。
自作が難しいと感じたら…おすすめのタブレット注文アプリ・サービス5選
ここまで自作の方法や可能性について詳しく解説してきましたが、「やっぱり自分にはハードルが高いかも…」と感じた方も少なくないでしょう。それは決して間違った判断ではありません。むしろ、本業に集中するために、プロが作った信頼性の高いサービスを利用するのは非常に賢明な選択です。
ここでは、自作の代替案として、多くの飲食店で導入実績があり、評判の高いおすすめのタブレット注文アプリ(セルフオーダーシステム)を5つ厳選してご紹介します。各サービスの特徴を比較し、あなたのお店に最適なものを見つけてください。
1. スマレジ・ウェイター
クラウドPOSレジの「スマレジ」が提供するセルフオーダーシステムです。POSレジとの完璧な連携が最大の強み。iPadとiPhoneがあればすぐに始められ、直感的な操作性が魅力です。
- 特徴:POSレジ「スマレジ」との完全連携、高度な売上分析、豊富な外部サービス連携。
- 料金:月額6,600円/1店舗〜(セルフオーダー機能)。別途スマレジのプラン料金が必要。
- こんなお店におすすめ:既にスマレジを導入している、または高機能なPOSレジと連携させて詳細な売上分析を行いたいお店。
2. Airレジ オーダー
リクルートが提供するPOSレジアプリ「Airレジ」と連携するセルフオーダーシステム。Airレジ自体は無料で使えるため、コストを抑えて導入したいお店に人気です。お客様が自身のスマートフォンで注文するモバイルオーダー形式が基本となります。
- 特徴:無料POSレジ「Airレジ」との連携、お客様のスマホを利用するため端末代が不要、導入の手軽さ。
- 料金:初期費用・月額費用は要問い合わせ。
- こんなお店におすすめ:初期費用を抑えたい小規模店舗、テイクアウトや店内でのモバイルオーダーを導入したいお店。
3. Square レストラン
決済サービスで有名なSquareが提供する、飲食店に特化したPOSレジ・オーダーシステムです。キャッシュレス決済との連携が非常にスムーズで、テーブルオーダーからオンライン注文まで幅広く対応しています。
- 特徴:スムーズなキャッシュレス決済連携、デリバリーやテイクアウトなど多様な注文形式に対応、分かりやすい料金体系。
- 料金:月額13,000円/1店舗〜(プラスプラン)。無料プランもあり。
- こんなお店におすすめ:キャッシュレス決済を強化したい、テイクアウトやデリバリーも一元管理したいお店。
4. Okage Order
Okage株式会社が提供する飲食店向けDXツールの一つ。セルフオーダーだけでなく、モバイルオーダー、セルフレジ、券売機など、店舗の課題に合わせて必要な機能を自由に組み合わせられるのが特徴です。
- 特徴:機能の自由な組み合わせ、多言語対応、食べ放題・飲み放題など複雑な注文への対応力。
- 料金:要問い合わせ。
- こんなお店におすすめ:お店の業態に合わせて柔軟にシステムを構築したい、食べ放題などを実施しているお店。
5. FoodTech Order
株式会社Restartzが提供する、LINEと連携したモバイルオーダーシステムです。お客様はLINEアプリから簡単に注文でき、お店側は友だち追加を促すことで、リピート販促に繋げやすいのが大きなメリットです。
- 特徴:LINEとの連携による高い利便性、再来店を促すメッセージ配信などの販促機能。
- 料金:月額10,780円〜。
- こんなお店におすすめ:LINEを活用して顧客との繋がりを強化し、リピーターを増やしたいお店。

ここで紹介したサービスはほんの一例です。多くのサービスで無料デモや資料請求が可能ですので、まずは気になるサービスに問い合わせて、実際にご自身の目で比較検討してみることをお勧めします!
タブレット注文システムの自作に関するQ&A
最後に、タブレット注文システムの自作に関して、多くの方が抱くであろう疑問についてQ&A形式でお答えします。これまでの内容の復習も兼ねて、ぜひご覧ください。
不可能ではありませんが、極めて困難な挑戦であると認識してください。まずはProgateやドットインストールといったオンライン学習サービスで、HTML, CSS, JavaScript, そして何らかのサーバーサイド言語(PythonやPHPなど)の基礎を学ぶところから始める必要があります。学習だけで最低でも半年から1年はかかると考えておきましょう。
もし本当にプログラミング未経験から挑戦するのであれば、この記事で紹介した「Googleフォームを活用する方法」から試してみるか、まずは既製品を導入して、その仕組みを理解してから自作を検討するのが現実的なステップと言えるでしょう。
セキュリティは自作において最も重要な課題の一つです。最低限、以下の対策は必須となります。
- SSL/TLS化:通信を暗号化し、データの盗聴や改ざんを防ぎます。URLが「https://」で始まるサイトはSSL化されています。
- SQLインジェクション対策:データベースへの不正な命令を防ぐためのプログラム上の対策です。
- クロスサイトスクリプティング(XSS)対策:悪意のあるスクリプトが埋め込まれるのを防ぐ対策です。
- パスワードのハッシュ化:データベースに保存するパスワードを暗号化し、万が一漏洩しても悪用されにくくします。
- ソフトウェアの定期的なアップデート:OSやミドルウェア、ライブラリなどを常に最新の状態に保ち、脆弱性をなくします。
特にクレジットカード情報など、機密性の高い情報を扱う場合は、専門家への相談を強く推奨します。
一概には言えませんが、安定稼働のためには継続的な保守が必要です。具体的には、少なくとも月に一度はサーバーのログを確認し、不審なアクセスがないか、エラーが発生していないかをチェックするのが望ましいです。また、前述のソフトウェアのアップデート情報は常にチェックし、脆弱性が発見された場合は速やかに対応する必要があります。
機能の追加や改善を行う場合は、その都度、開発とテストの時間が必要になります。「作って終わり」ではなく、「育てていく」という意識を持つことが大切です。
はい、信頼できる販売店から購入した高品質な中古タブレットであれば、全く問題ありません。重要なのは、あまりに古いモデルを選ばないことです。OSのバージョンが古すぎると、セキュリティ上のリスクがあったり、最新のWeb技術に対応できなかったりする場合があります。一般的には、発売から3〜4年以内のモデルを選ぶと良いでしょう。
この記事でもご紹介した「にこスマ」のような、厳格な検査基準と長期保証を設けている販売店を利用すれば、安心して中古タブレットを導入できます。コスト削減と安心を両立させるためにも、ぜひ活用を検討してみてください。
まとめ:あなたのお店に最適な一歩を踏み出そう
今回は、「タブレット注文システムの自作」をテーマに、その可能性から具体的な方法、メリット・デメリット、そして代替案となる既製品サービスまで、網羅的に解説してきました。
記事の要点をもう一度振り返ってみましょう。
- タブレット注文システムの自作は可能だが、相応の技術力と時間が必要。
- 自作の最大のメリットは、コスト削減と自由なカスタマイズ性。
- 一方、保守・運用の負担やセキュリティリスクという大きなデメリットも存在する。
- プログラミングが難しい場合でも、Googleフォームなどを活用して無料で仕組みを構築する方法もある。
- 自作に挑戦するなら、スモールスタートで始め、徐々に拡張していくのが成功の鍵。
- 自作が困難な場合は、スマレジやAirレジなどの信頼できる既製品サービスを検討するのが賢明。
- 導入コストを抑えるには、「にこスマ」のような高品質な中古タブレットの活用が非常に有効。
この記事を読んで、あなたは「よし、自作に挑戦してみよう!」と決意を固めたかもしれません。あるいは、「まずは既製品で確実に業務を効率化しよう」と考えたかもしれません。どちらの選択も、あなたのお店をより良くするための一歩であり、決して間違いではありません。
大切なのは、ご自身のお店の状況、スキル、そして将来のビジョンを冷静に見つめ、最適な判断を下すことです。
もし自作の道を選ぶなら、この記事があなたのロードマップとして役立つことを願っています。もし既製品を選ぶなら、ここで得た知識が、数あるサービスの中から最適なものを見つけ出すための羅針盤となるはずです。
さあ、まずはあなたのお店が抱える課題を洗い出し、それを解決するための最適な一歩を踏み出しましょう! あなたの挑戦を心から応援しています。