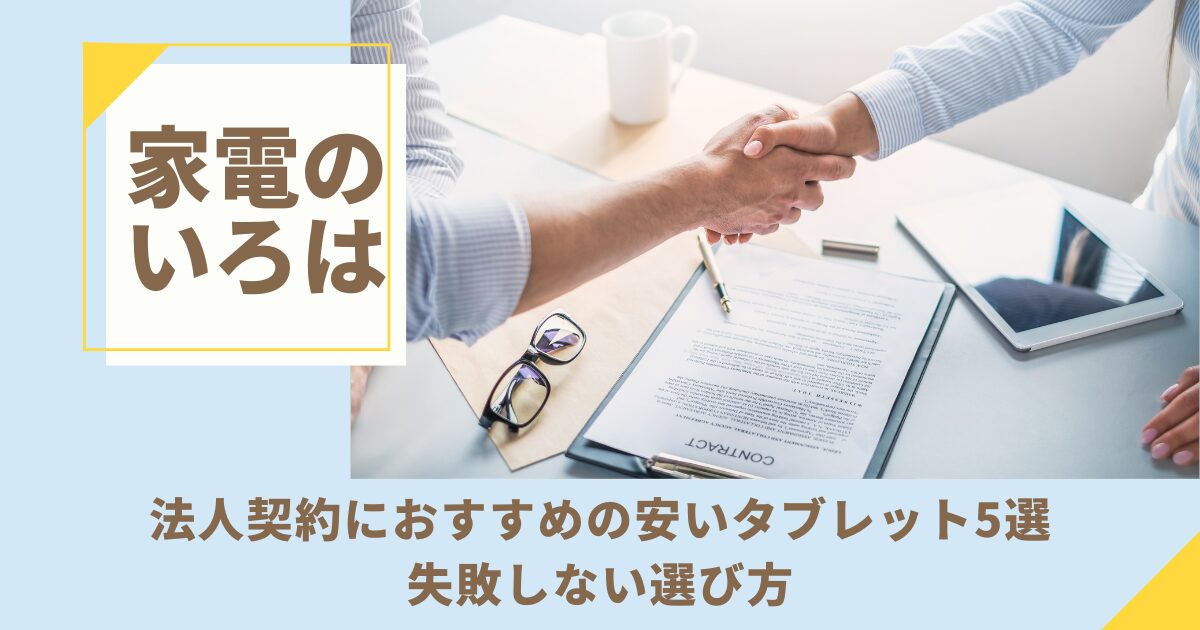「業務効率化のためにタブレットを導入したいけど、コストはできるだけ抑えたい…」
「タブレットを法人契約したいけど、種類が多すぎてどれが自社に合っているのか分からない…」
「購入、リース、レンタル…どの契約方法が一番安くてお得なの?」
このようなお悩みを抱えていませんか?
近年、働き方改革やDX推進の流れを受け、多くの企業でタブレットの導入が加速しています。しかし、いざ導入を検討すると、機種選びや契約方法の複雑さに頭を悩ませる担当者様は少なくありません。特に、コストは企業にとって最重要課題の一つですよね。
ご安心ください。この記事では、「タブレットを法人契約で安く導入したい」とお考えのあなたのために、以下の内容を徹底的に解説します。
- 法人向けタブレットと個人向けモデルの具体的な違い
- 購入・リース・レンタルのメリット・デメリットと最適な選び方
- コストを抑えつつ自社に合ったタブレットを選ぶための5つの重要ポイント
- 安くて高性能!法人におすすめのタブレット5選
- 導入コストを劇的に下げる「中古タブレット」という賢い選択肢
この記事を最後まで読めば、あなたの会社に最適なタブレットを、最もコストパフォーマンスの高い方法で導入するための知識がすべて手に入ります。経費を抑えながら業務効率を最大化する、その第一歩をここから踏み出しましょう。
- なぜ今、法人契約でタブレット導入が急増しているのか?
- 【基本のキ】法人向けタブレットと個人向けモデルの決定的な違い
- 法人でタブレットを導入する3つの方法!購入・リース・レンタルの違いを徹底比較
- 法人契約で安いタブレットを選ぶための5つの重要ポイント
- 安い!法人契約におすすめのタブレット5選
- 【裏ワザ】中古タブレット活用で導入コストを劇的に下げる方法
- 法人のタブレット契約で失敗しない!通信キャリア・格安SIMの選び方
- 導入後の管理・運用を効率化するMDM(モバイルデバイス管理)とは?
- 【業種別】法人タブレット活用事例とおすすめモデル
- 法人タブレットの契約に関するよくある質問(Q&A)
- まとめ:最適な一台を見つけてビジネスを加速させよう!
なぜ今、法人契約でタブレット導入が急増しているのか?
まず初めに、なぜ多くの企業がタブレット導入に注目しているのか、その理由を深掘りしてみましょう。単なる流行ではなく、企業の成長に直結する明確なメリットが存在します。「うちの会社でも本当に役立つの?」という疑問も、ここで解消されるはずです。

劇的な業務効率化の実現【ペーパーレス化と迅速な情報共有】
タブレット導入による最大のメリットは、何と言っても業務効率の飛躍的な向上です。これまで紙媒体で行っていた業務をデジタル化することで、時間とコストの両面で大きな効果が期待できます。
具体的には、以下のような変化が起こります。
- ペーパーレス化の推進
会議資料や報告書、契約書などを全てデジタルデータで管理できます。これにより、印刷にかかるインク代や用紙代、保管スペースといった物理的なコストを大幅に削減可能です。また、必要な書類を瞬時に検索できるため、資料探しの時間もなくなります。 - 情報共有のスピードアップ
クラウドサービスと連携すれば、全社員がいつでもどこでも最新の情報にアクセスできます。営業担当者が外出先で作成した報告書を、オフィスにいる上司がリアルタイムで確認・承認するといったスピーディな連携が可能です。これにより、意思決定の速度が格段に向上します。 - 入力作業の効率化
手書きだったアンケートや日報を、タブレットの入力フォームに切り替えることで、データ入力の手間や転記ミスがなくなります。収集したデータは自動で集計・分析できるため、マーケティング戦略などにも活かしやすくなります。
これらの変化は、一つ一つは小さなものに見えるかもしれません。しかし、組織全体で取り組むことで、生産性を大きく向上させ、社員がより創造的な業務に集中できる環境を生み出すのです。
多様な働き方への柔軟な対応【テレワークや現場作業の強化】
現代のビジネス環境では、テレワークやハイブリッドワークといった多様な働き方への対応が不可欠です。タブレットは、その携帯性の高さから、場所を選ばない働き方を強力にサポートします。
例えば、建設業や不動産業の現場では、重たい紙の図面や資料を持ち運ぶ必要がなくなります。タブレット一つで大量の図面を管理し、その場で修正指示を書き込んだり、写真を撮影して報告書を作成したりできます。これにより、現場とオフィスの連携がスムーズになり、作業効率が大幅にアップします。
また、営業職においては、顧客先で動画やリッチなコンテンツを使った魅力的なプレゼンテーションが可能になります。分厚いカタログを持ち歩く必要もなく、顧客の質問に応じて即座に関連資料を提示できるため、商談の質も向上するでしょう。テレワーク中の社員も、オフィスにいるのと変わらない環境で資料の閲覧やWeb会議への参加ができ、生産性を維持できます。
顧客満足度の向上【スムーズな接客と先進的な企業イメージ】
タブレットは、社内の業務効率化だけでなく、顧客との接点においても大きな価値を発揮します。
- 飲食・小売業界での活用
飲食店では、お客様自身がテーブルのタブレットで注文するセルフオーダーシステムを導入することで、注文ミスを防ぎ、スタッフの負担を軽減できます。小売店では、在庫確認や商品説明にタブレットを活用し、お客様を待たせることなくスムーズな接客が可能です。 - 対面でのプレゼンテーション
保険の契約や不動産の案内など、対面での説明が必要な場面で、タブレットを使えば視覚的に分かりやすい説明ができます。動画やシミュレーションを交えることで、顧客の理解度を深め、納得感を高めることができます。 - 先進的な企業イメージの構築
業務にタブレットをスマートに活用している姿は、顧客に対して「ITを駆使した先進的な企業」というポジティブな印象を与えます。これは、企業のブランドイメージ向上にも繋がる重要な要素です。
このように、タブレット導入は業務効率化に留まらず、働き方の変革、顧客満足度の向上、そして企業価値の向上にまで貢献する、非常に費用対効果の高い投資と言えるでしょう。
【基本のキ】法人向けタブレットと個人向けモデルの決定的な違い
「家電量販店で売っている個人向けの安いタブレットではダメなの?」これは多くの担当者様が抱く疑問です。結論から言うと、ビジネスで利用するなら法人向けモデルを選ぶのが賢明です。一見同じように見えるタブレットですが、法人向けモデルにはビジネス利用を想定した重要な違いがいくつもあります。ここでは、その決定的な違いを4つのポイントに分けて解説します。
違い①:セキュリティ機能【会社の情報を守るための要】
法人利用で最も重視すべきなのがセキュリティです。タブレットには顧客情報や社外秘のデータなど、企業の重要な情報資産が保存されます。万が一、紛失や盗難、ウイルス感染によって情報が漏洩すれば、企業の信頼は失墜し、甚大な損害を被る可能性があります。
法人向けタブレットは、こうしたリスクに対応するため、以下のような強力なセキュリティ機能を備えています。
- MDM(モバイルデバイス管理)への対応
MDMとは、複数のタブレットを一元管理するためのシステムです。管理者は、遠隔で各端末の利用状況を監視し、業務に不要なアプリのインストールを制限したり、万が一の紛失時には遠隔でデータを消去(リモートワイプ)したりできます。個人向けモデルでは、このMDMに完全に対応していない場合があります。 - 強固なデータ暗号化
法人向けモデルは、端末内のデータを高度に暗号化する機能が強化されています。これにより、たとえ端末が分解されてストレージが抜き取られたとしても、第三者がデータを読み取ることは極めて困難です。 - OSのカスタマイズ性
特定の機能のみを利用できるようにOSをカスタマイズ(キオスクモード化)できるモデルもあります。例えば、店舗の展示用端末として、特定のアプリ以外は起動できないように設定することが可能です。
違い②:サポート体制【万が一のトラブルでも業務を止めない】
業務で使うタブレットが故障した場合、修理に何週間もかかっていては仕事になりませんよね。法人向けモデルは、「業務を止めない」ための手厚いサポート体制が用意されています。
- 法人専用のサポート窓口
トラブルが発生した際に、専門知識を持ったスタッフが迅速に対応してくれる法人専用のヘルプデスクが設けられています。電話やチャット、メールなど、複数の連絡手段が用意されていることがほとんどです。 - 代替機貸し出しサービス
修理期間中、業務が滞らないように代替機を迅速に貸し出してくれるサービスがあります。これにより、社員はすぐに業務を再開できます。個人向けモデルの修理では、代替機の提供がないか、あっても有料の場合が多いです。 - 延長保証・オンサイト修理
通常のメーカー保証よりも長期間の保証を提供するプランや、エンジニアが直接会社まで訪問して修理を行う「オンサイト修理」サービスを選べる場合もあります。
これらのサポートは、目に見えるスペックではありませんが、安心して業務を継続するための重要な保険と言えるでしょう。

違い③:耐久性と堅牢性【ハードな業務用に耐える設計】
オフィス内だけでなく、建設現場や工場、店舗のバックヤードなど、様々な環境で利用される法人向けタブレットは、個人向けモデルよりも高い耐久性・堅牢性が求められます。
例えば、落下時の衝撃に強い耐衝撃性能や、水滴やホコリの侵入を防ぐ防塵・防滴性能を備えたモデルが多くラインナップされています。特に「TOUGHBOOK」のような堅牢タブレットは、米国国防総省の調達基準である「MIL規格」に準拠しており、非常に過酷な環境でも安定して動作するように設計されています。
また、長時間の連続使用を想定し、バッテリーの耐久性や排熱性能が強化されている点も特徴です。故障のリスクを低減し、長期的に安定して利用できることは、結果的にトータルコストの削減に繋がります。
違い④:キッティングサービス【導入時の手間を大幅に削減】
数十台、数百台のタブレットを導入する際、一台ずつ箱から出して、Wi-Fi設定やアプリのインストール、各種アカウント設定を行うのは非常に手間がかかります。この導入時の初期設定作業を代行してくれるのが「キッティングサービス」です。
法人向けの販売代理店では、このキッティングサービスが提供されていることが一般的です。企業の情報システム担当者は、煩雑な設定作業から解放され、本来の業務に集中できます。端末が届いたら、すぐに社員に配布して利用を開始できるため、スムーズな導入が可能です。
このように、法人向けタブレットは価格だけでは見えない部分で、ビジネス利用に最適化された機能やサービスが充実しています。初期費用が多少高くても、長期的な視点で見れば、セキュリティ、運用、管理の面で大きなメリットがあるのです。
法人でタブレットを導入する3つの方法!購入・リース・レンタルの違いを徹底比較
法人でタブレットを導入する方法は、大きく分けて「購入」「リース」「レンタル」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、どの方法が最適かは企業の状況や利用目的によって異なります。「とにかく安く」と考えるなら、それぞれの特徴を正しく理解し、比較検討することが不可欠です。ここでは、あなたの会社に最適な方法を見つけるために、3つの導入方法を徹底的に比較・解説します。
【所有権重視派】購入のメリット・デメリット
「購入」は、その名の通り、タブレットを自社の資産として買い取る方法です。最もシンプルな方法ですが、メリットとデメリットをしっかり把握しておく必要があります。
購入のメリット
- 長期的には最も安くなる可能性がある:一度支払ってしまえば、その後の月額費用はかかりません(通信費は除く)。長期間(例えば4〜5年以上)同じ端末を使い続けるのであれば、リースやレンタルよりも総支払額は安くなるケースが多いです。
- 資産として計上できる:購入したタブレットは会社の資産となるため、減価償却による経費計上が可能です。
- カスタマイズの自由度が高い:自社の所有物なので、アプリのインストールや設定変更などを自由に行えます。
購入のデメリット
- 初期費用が高額になる:特に数十台、数百台をまとめて導入する場合、一度に多額の現金が必要となり、キャッシュフローを圧迫する可能性があります。
- 管理・処分の手間がかかる:固定資産としての管理や、古くなった際の廃棄・処分は自社で行う必要があり、手間とコストがかかります。
- 陳腐化のリスク:数年経つと端末の性能が時代遅れ(陳腐化)になりますが、資産であるため簡単に買い替えることが難しい場合があります。
【コスト平準化派】リースのメリット・デメリット
「リース」は、リース会社が企業に代わってタブレットを購入し、それを企業が月額料金で長期間(通常3年〜5年)借りる契約形態です。所有権はリース会社にあります。
リースのメリット
- 初期費用が不要:購入時に必要なまとまった資金が不要で、導入のハードルが大幅に下がります。
- コストを平準化できる:毎月の支払いが一定額なので、経費処理が容易になり、予算計画も立てやすくなります。
- 最新機種を導入しやすい:リース期間が終了すれば、新しい契約を結んで最新機種に入れ替えることができます。陳腐化のリスクを回避できます。
- 固定資産税がかからない:所有権はリース会社にあるため、固定資産税の支払い義務がありません。
リースのデメリット
- 総支払額は購入より割高になる:月額料金には、本体価格に加えて金利や手数料が含まれるため、総支払額は購入するよりも高くなります。
- 中途解約が原則不可:契約期間中の解約は原則としてできず、もし解約する場合は残りのリース料を一括で支払う必要があります。
- 所有権がない:契約終了後は、端末をリース会社に返却する必要があります(再リースや買取オプションがある場合も)。
【短期利用派】レンタルのメリット・デメリット
「レンタル」は、レンタル会社が保有しているタブレットを、必要な期間だけ借りるサービスです。数日単位や月単位といった短期間での利用に適しています。
レンタルのメリット
- 超短期間から利用可能:イベントや研修、繁忙期の臨時業務など、必要な時に必要な台数だけ借りることができます。
- 契約・解約の自由度が高い:リースと異なり、契約期間の縛りが緩やかで、中途解約も比較的容易です。
- メンテナンス不要:故障時の修理や交換はレンタル会社が行ってくれるため、管理の手間がかかりません。
レンタルのデメリット
- 長期間の利用は割高になる:1日あたりや1ヶ月あたりの単価はリースよりも高く設定されているため、長期間利用すると総支払額が非常に高額になります。
- 機種を選べない場合がある:レンタル会社が保有している在庫の中から選ぶため、希望する最新機種や特定のスペックの端末が利用できないことがあります。
- 中古品の場合が多い:新品ではなく、整備された中古品(リファービッシュ品)が提供されることがほとんどです。
あなたの会社に最適なのは?選び方のまとめ
結局どの方法が良いのか、下の表で自社の状況と照らし合わせてみましょう。
| 項目 | 購入 | リース | レンタル |
|---|---|---|---|
| おすすめの企業 | 初期投資の資金に余裕があり、長期的に利用する予定の企業 | 初期費用を抑え、コストを平準化したい企業。定期的に最新機種を使いたい企業 | イベントや研修など、特定の期間だけ利用したい企業 |
| 初期費用 | 高額 | 不要 | 不要 |
| 月額費用 | なし(通信費等は除く) | 一定額 | 割高 |
| 総支払額 | 最も安い | 割高 | 非常に割高 |
| 契約期間 | なし | 長期(3年〜5年) | 短期(1日〜) |
| 中途解約 | – | 原則不可 | 可能 |
| 所有権 | 自社 | リース会社 | レンタル会社 |
「初期費用を抑えたい」「経費処理を楽にしたい」「常に新しい機種を使いたい」というニーズが強い場合はリースが最も適しています。一方で、「数日のイベントで50台必要」といったスポット的な利用であればレンタルが最適です。資金に余裕があり、「とにかく総支払額を安くしたい」のであれば購入が良いでしょう。最近では、後述する「中古品の購入」という選択肢もコスト削減の観点から非常に注目されています。
法人契約で安いタブレットを選ぶための5つの重要ポイント
「安い」という言葉だけに惹かれてタブレットを選ぶと、「動作が遅すぎて仕事にならない」「必要なアプリが使えなかった」といった失敗に繋がりかねません。コストを抑えつつ、業務でしっかり使えるタブレットを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、法人タブレット選びで絶対に外せない5つのポイントを詳しく解説します。
ポイント1:利用目的に合ったスペックを見極める
最も重要なのは「何のために使うのか」を明確にすることです。用途によって必要なスペック(性能)は大きく異なります。オーバースペックな高価なモデルを選んでも宝の持ち腐れですし、逆にスペック不足では業務効率が低下してしまいます。
- Web閲覧・メール・簡単な資料作成が中心の場合
エントリーモデルのスペックで十分です。CPUは標準的なもので、メモリ(RAM)は4GB程度、ストレージは64GBもあれば問題ないでしょう。この用途であれば、価格を最優先に考えても失敗は少ないです。 - 高画質な動画の再生や、少し複雑なアプリを利用する場合
ミドルレンジのモデルがおすすめです。メモリは6GB~8GB、ストレージは128GB以上あると安心です。画面の解像度もチェックしておくと、より快適に利用できます。 - 動画編集やCAD図面の閲覧など、高い処理能力が必要な場合
ハイエンドモデルを選ぶ必要があります。最新の高性能CPUを搭載し、メモリは8GB以上、ストレージも256GB以上が望ましいです。価格は高くなりますが、ここで妥協すると作業効率に直結します。
社内の利用者にヒアリングを行い、具体的な使い方をリストアップすることから始めましょう。
ポイント2:OS(iPadOS, Android, Windows)の特性を理解する
タブレットのOSは、主に3種類あります。それぞれに特徴があり、業務内容や既存の社内システムとの連携を考慮して選ぶことが重要です。
| OS | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| iPadOS (Apple) | 直感的で分かりやすい操作性。高品質でビジネス向けのアプリが豊富。 | ・操作が簡単で誰でも使いやすい ・セキュリティが高い ・デザイン性が高く、顧客への印象が良い |
・本体価格が比較的高価 ・SDカードでストレージを拡張できない |
| Android (Google) | 様々なメーカーから多様な価格帯の端末が発売されている。カスタマイズ性が高い。 | ・安価なモデルが多い ・機種の選択肢が非常に豊富 ・SDカードが使える機種が多い |
・メーカーによって操作性が異なる ・セキュリティ面で若干の不安が残る場合も |
| Windows (Microsoft) | 普段使っているPCと同じ感覚で操作できる。Officeソフトとの親和性が非常に高い。 | ・PC版のOfficeがそのまま使える ・既存の業務システムと連携しやすい ・USBポートなど拡張性が高い |
・アプリの数が少ない ・本体が比較的重く、価格も高め |
例えば、「社員のITリテラシーに差がある」「とにかく操作が簡単なものが良い」という場合はiPadOSがおすすめです。「コストを最優先したい」「特定の業務に特化してカスタマイズしたい」という場合はAndroidが有力候補になります。「ExcelやWordをPCと同じように使いたい」というニーズが強ければWindowsタブレットが最適です。
ポイント3:Wi-Fiモデルかセルラーモデルか?通信環境で選ぶ
タブレットには、Wi-Fi環境下でのみインターネットに接続できる「Wi-Fiモデル」と、SIMカードを挿入して単体でデータ通信が可能な「Wi-Fi + Cellularモデル」があります。
- Wi-Fiモデル
主にオフィスや店舗内など、Wi-Fi環境が整っている場所で利用する場合におすすめです。セルラーモデルに比べて本体価格が安く、月々の通信費もかからないのが最大のメリットです。外出先で使いたい場合は、スマートフォンのテザリング機能やモバイルWi-Fiルーターを利用する方法があります。 - Wi-Fi + Cellularモデル
営業や現場作業など、外出先で頻繁にインターネットを利用する業務に適しています。いつでもどこでも通信できるため、利便性が非常に高いです。ただし、本体価格がWi-Fiモデルより1.5〜2万円ほど高くなる上、別途データ通信プランの契約と月額料金が必要になります。
利用シーンを具体的に想定し、「本当にセルラー機能が必要か?」を慎重に検討することがコスト削減に繋がります。
ポイント4:セキュリティ対策は万全か?MDM連携も視野に
法人向けと個人向けの違いでも触れましたが、セキュリティは絶対に妥協してはならないポイントです。特に安いタブレットを選ぶ際には、セキュリティ機能が省略されていないか注意が必要です。
確認すべき点として、「MDM(モバイルデバイス管理)」に正式に対応しているかは必ずチェックしましょう。MDMを導入することで、複数台のタブレットのセキュリティポリシーを統一し、一元管理することが可能になります。将来的に台数を増やす可能性があるなら、MDM対応は必須条件と考えておきましょう。
ポイント5:導入後のサポート体制を確認する
「安物買いの銭失い」にならないために、サポート体制の確認も重要です。故障した際の修理受付はどこになるのか、代替機の貸し出しはあるのか、保証期間は何年か、といった点を事前に確認しておきましょう。特に海外メーカーの安価なタブレットの場合、サポート窓口が国内になかったり、対応が遅かったりするケースもあります。万が一の際に業務に支障が出ないよう、信頼できるメーカーや販売代理店から購入・契約することを強くおすすめします。

安い!法人契約におすすめのタブレット5選
ここまでの選び方のポイントを踏まえ、いよいよ具体的なおすすめ機種をご紹介します。今回は「安さ」をテーマに、コストパフォーマンスに優れ、かつビジネスシーンで十分な性能を発揮する5つのタブレットを厳選しました。それぞれの特徴を比較し、自社に最適な一台を見つけてください。
【コスパ最強の王道】iPad(第10世代)
法人タブレットで最も選ばれていると言っても過言ではないのが、AppleのiPad(無印)です。直感的な操作性で誰でもすぐに使いこなせる点、高品質で豊富なビジネスアプリ、そして高いセキュリティ性能が評価されています。ProやAirといった上位モデルに比べて価格が抑えられており、コストと性能のバランスが非常に優れています。
- おすすめの理由:
- 簡単な操作性:IT機器が苦手な社員でも教育コストをかけずに導入できます。
- 高いリセールバリュー:数年後に買い替える際も、中古市場で高く売れるため、実質的なコストを抑えられます。
- 豊富な周辺機器:専用のキーボードやApple Pencilなど、用途を広げるアクセサリが充実しています。
- 主なスペック:
- OS:iPadOS
- ディスプレイ:10.9インチ Liquid Retinaディスプレイ
- CPU:A14 Bionicチップ
- ストレージ:64GB / 256GB
- 価格帯:68,800円(税込)~
- こんな企業におすすめ:社員のITリテラシーにばらつきがある企業、顧客へのプレゼンなど対外的な利用が多い企業。
【Androidの定番】Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
Androidタブレットの中で、コストと性能のバランスで人気が高いのがLenovoのTabシリーズです。特にM10 Plusは、10.6インチの大画面と十分な基本性能を備えながら、4万円台から購入可能という驚異的なコストパフォーマンスを誇ります。
- おすすめの理由:
- 圧倒的な安さ:iPadと比較して、大幅に導入コストを削減できます。
- Google系サービスとの連携:Google Workspaceなどをメインで利用している企業にとっては、親和性が高く使いやすいです。
- MicroSDカード対応:安価なMicroSDカードでストレージを簡単に増設できるため、写真や動画を多く扱う業務にも対応できます。
- 主なスペック:
- OS:Android
- ディスプレイ:10.61インチ 2K IPS液晶
- CPU:Qualcomm Snapdragon 680
- ストレージ:64GB / 128GB
- 価格帯:40,000円(税込)~
- こんな企業におすすめ:とにかく初期費用を抑えたい企業、倉庫での在庫管理や店舗での簡易POSレジなど、特定の用途で大量導入したい企業。
【Windows搭載でPCライク】Microsoft Surface Go 3
「タブレットの手軽さとノートPCの作業性を両立したい」というニーズに完璧に応えるのがSurface Go 3です。OSにWindows 11を搭載しているため、普段オフィスで使っているPCと全く同じ感覚で操作できます。特に、PC版のExcelやWord、PowerPointがそのまま使える点は、他のOSにはない大きなアドバンテージです。
- おすすめの理由:
- Officeソフトとの完全な互換性:マクロや複雑な関数を使ったExcelファイルも、表示崩れなく編集・作成できます。
- PCと同じ操作感:新たな操作を覚える必要がなく、導入がスムーズに進みます。
- 豊富なインターフェース:USB-CポートやmicroSDXCカードリーダーを備え、拡張性も十分です。
- 主なスペック:
- OS:Windows 11
- ディスプレイ:10.5インチ PixelSense ディスプレイ
- CPU:Intel Pentium Gold / Core i3
- ストレージ:64GB / 128GB / 256GB
- 価格帯:70,000円(税込)~
- こんな企業におすすめ:外出先でもOfficeソフトを使った本格的なドキュメント作成を行いたい企業、既存のWindowsベースの業務システムと連携させたい企業。
【堅牢性が魅力】Panasonic TOUGHBOOK FZ-L1
建設現場や工場、配送業など、ハードな環境での利用を想定するなら、Panasonicの堅牢タブレット「TOUGHBOOK」シリーズが最適です。FZ-L1は7インチと小型ながら、耐落下1.5m、防塵・防滴IP67準拠という高い堅牢性を誇ります。多少の雨やホコリ、衝撃にもびくともしないため、屋外作業でも安心して利用できます。
- おすすめの理由:
- 圧倒的なタフ性能:故障による業務停止リスクと修理コストを最小限に抑えます。
- 手袋でも操作可能:手袋を装着したままでもタッチ操作ができるモードを搭載しており、作業を中断させません。
- バーコードリーダー搭載:オプションでバーコードリーダーを内蔵でき、検品や在庫管理業務を効率化します。
- 主なスペック:
- OS:Android
- ディスプレイ:7.0インチHD
- CPU:Qualcomm MSM8909
- ストレージ:16GB
- 価格帯:要問い合わせ(法人向け販売のみ)
- こんな企業におすすめ:建設、物流、製造、インフラ点検など、屋外や過酷な環境でタブレットを利用する企業。
【低価格で導入】Amazon Fire HD 10
Amazonが開発するFireタブレットは、エンターテイメント用途のイメージが強いですが、その圧倒的な低価格から、用途を限定した法人利用でも注目されています。10.1インチの大画面モデル「Fire HD 10」でも2万円を切る価格は、他の追随を許しません。
- おすすめの理由:
- 驚異的な低価格:大量導入時のコストを劇的に削減できます。
- 十分な基本性能:Webブラウジングや動画再生、電子書籍の閲覧といった用途であれば、ストレスなく動作します。
- 注意点:
- OSはAndroidベースの独自OS「Fire OS」であり、Google Playストアが利用できません。アプリはAmazonアプリストアからインストールする必要があります。業務で必須のアプリが対応しているか、事前の確認が不可欠です。
- 主なスペック:
- OS:Fire OS
- ディスプレイ:10.1インチ フルHD
- CPU:8コアプロセッサ
- ストレージ:32GB / 64GB
- 価格帯:19,980円(税込)~
- こんな企業におすすめ:店舗でのデジタルサイネージ、待合室での動画再生、マニュアル閲覧用端末など、利用目的が明確に限定されている企業。
【裏ワザ】中古タブレット活用で導入コストを劇的に下げる方法
「新品にこだわりはない」「とにかく初期費用を1円でも安く抑えたい!」そうお考えの担当者様にとって、「中古タブレット」は非常に強力な選択肢となります。一昔前は「安かろう悪かろう」というイメージもあった中古品ですが、現在では品質管理や保証が徹底された信頼できる販売店が増えており、法人での導入事例も急増しています。ここでは、中古タブレットを活用するメリットと、安心して購入できるサービスの選び方を解説します。
なぜ今、法人で中古タブレットが注目されているのか?
注目される理由はシンプルです。それは、新品に比べて圧倒的に安く、かつ業務利用には十分すぎる性能の端末が手に入るからです。タブレットの性能は年々向上していますが、Web閲覧やメール、簡単な資料作成といった一般的な業務であれば、2〜3年前のモデルでも全く問題なく快適に動作します。
例えば、最新のiPadを1台購入する予算で、高品質な中古のiPadが2台購入できるケースも珍しくありません。これにより、同じ予算でより多くの社員にタブレットを配布したり、捻出した予算を他のIT投資に回したりすることが可能になります。
中古タブレット導入のメリットと注意点
メリット
- 圧倒的なコスト削減効果:新品の半額以下で購入できるモデルも多く、導入費用を大幅に圧縮できます。
- 豊富な選択肢:販売が終了したモデルや、特定のスペックを持つ旧モデルなど、新品市場にはない端末も選択肢に入ります。
- SDGsへの貢献:リユース品を活用することは、電子廃棄物を削減し、持続可能な社会の実現に貢献する企業の姿勢を示すことにも繋がります。
注意すべきデメリットと信頼できる販売店の選び方
もちろん、中古品ならではの注意点もあります。個人間の売買や信頼性の低いショップで購入すると、「バッテリーがすぐに切れる」「赤ロム(ネットワーク利用制限)だった」「傷や汚れがひどい」といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。
だからこそ、法人で中古タブレットを導入する際は、信頼できる販売店を選ぶことが絶対条件です。以下のポイントを必ずチェックしましょう。
- 運営会社は信頼できるか?:企業のバックボーンがしっかりしているかを確認します。
- 品質チェックは徹底されているか?:専門家による厳格な機能検査やクリーニングが行われているか。
- 赤ロム保証はあるか?:万が一、ネットワーク利用制限がかかった場合に保証してくれるか。
- 長期の動作保証はあるか?:初期不良だけでなく、長期間の動作保証が付いていると安心です。
- サポート体制は整っているか?:購入後の問い合わせに対応してくれる窓口があるか。

伊藤忠グループ運営「にこスマ」なら高品質で安心!
「じゃあ、具体的にどこで買えば安心なの?」という声にお応えして、私が自信を持っておすすめするのが、伊藤忠グループの株式会社Belongが運営する中古スマホ・タブレットのECサイト「にこスマ」です。
「にこスマ」は、上記で挙げた「信頼できる販売店の条件」を全て高いレベルで満たしており、法人担当者様にも安心してご利用いただけます。
にこスマをおすすめする3つの理由
- 伊藤忠グループ運営という絶対的な安心感
まず何よりも、大手総合商社である伊藤忠グループが運営しているという点が大きな信頼に繋がります。コンプライアンスや品質管理の基準が非常に高く、安心して取引できます。 - 初めてでも安心の「三つ星品質」
「にこスマ」で販売されている端末は、画面や本体に割れ・欠けがない、厳しい基準をクリアした端末のみを厳選しています。さらに、最先端の検査システムによって、Wi-Fi、カメラ、各種ボタンの動作など、25項目以上もの機能検査をパスしたものだけが「三つ星品質」として販売されます。外観だけでなく、中身までしっかりチェックされているので安心です。 - 1年間の無料返品交換保証と手厚いサポート
万が一、端末に不具合があった場合でも、購入から1年間は無料で返品・交換に対応してくれます。これは中古品としては異例の手厚い保証です。また、メールや電話、チャットでのサポート窓口も用意されているため、購入前の相談から購入後のトラブルまで、気軽に対応してもらえます。
さらに、「にこスマ」で取り扱っているのは全てSIMフリー端末で、ネットワーク利用制限の心配もありません。どの通信キャリアのSIMでも利用できるため、法人契約の通信プランに合わせて柔軟に選択できます。
コスト削減は企業の至上命題です。「にこスマ」のような信頼できるサービスを活用することで、品質や安心感を犠牲にすることなく、タブレットの導入コストを劇的に抑えることが可能です。ぜひ一度、公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。
法人のタブレット契約で失敗しない!通信キャリア・格安SIMの選び方
セルラーモデルのタブレットを導入する場合、本体とは別に通信契約が必要になります。この通信コストも、毎月発生するランニングコストとして軽視できません。大手キャリアの法人プランから、コストを抑えられる格安SIMまで、選択肢は様々です。ここでは、通信契約で失敗しないためのポイントを解説します。
大手3キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)の法人プラン比較
NTTドコモ、au (KDDI)、ソフトバンクの大手3キャリアは、それぞれ特色のある法人向けプランを提供しています。
大手キャリアのメリット
- 通信品質の安定性:全国をカバーする広い通信エリアと、安定した高速通信は最大の魅力です。
- 手厚いサポート:法人専門の営業担当がついたり、全国のショップで対面サポートが受けられたりと、サポート体制が充実しています。
- 豊富なオプションサービス:MDMサービスやセキュリティサービスなど、ビジネスに役立つ多様なオプションをワンストップで契約できます。
大手キャリアのデメリット
- 料金が割高:格安SIMと比較すると、月額の通信料金は高めに設定されています。
各社の特徴を簡単にまとめると以下のようになります。
| キャリア | 特徴 |
|---|---|
| NTTドコモ | 業界No.1の契約者数を誇り、通信エリアの広さと品質に定評があります。特に山間部や地方での通信の安定性は抜群です。 |
| au (KDDI) | オフィス向けの固定通信やクラウドサービスなど、通信以外のソリューションも豊富に提供しており、まとめて導入したい企業におすすめです。 |
| ソフトバンク | 独自の割引キャンペーンや、複数回線をまとめて契約する際のボリュームディスカウントに積極的で、コスト削減の提案力が高いのが特徴です。 |
通信の安定性やサポートを最重視する場合は、大手キャリアが安心です。複数のキャリアから相見積もりを取り、自社の利用状況に合ったプランを提案してもらうのが良いでしょう。
コストを抑えるなら「法人向け格安SIM」という選択肢
月々の通信コストを少しでも安くしたいなら、「法人向け格安SIM」が非常に有力な選択肢になります。格安SIM(MVNO)は、大手キャリアの通信網を借りてサービスを提供しているため、通信品質は同等でありながら、はるかに安い料金プランを実現しています。
法人向け格安SIMのメリット
- 圧倒的な低価格:大手キャリアの半額以下の料金で利用できるプランも多く、大幅なコスト削減が可能です。
- 柔軟なプラン:データ容量を複数のSIMでシェアできるプランや、通信速度を制限する代わりに低価格で提供するプランなど、ユニークで柔軟な料金体系が魅力です。
法人向け格安SIMのデメリット
- サポート体制:対面サポートを受けられる店舗が少ない、または無い場合が多く、基本的にオンラインでの手続きやサポートが中心となります。
- キャリアメールが使えない:大手キャリアが提供する「@docomo.ne.jp」のようなメールアドレスは利用できません。(ビジネス利用では独自ドメインのメールを使うことがほとんどなので、問題になるケースは少ないでしょう)
IIJmioやmineo、楽天モバイルなどが法人向けプランを提供しています。特に、普段の通信量は少ないが、たまに大容量通信が必要になる、といった不規則な使い方をする場合には、格安SIMの柔軟なプランがフィットしやすいです。
データ容量はどれくらい必要?利用シーン別目安
契約するデータ容量もコストに直結します。多すぎれば無駄になりますし、少なすぎると速度制限がかかり業務に支障をきたします。利用シーン別に必要なデータ容量の目安を把握しておきましょう。
- 1GB〜3GB/月:テキストベースのメール送受信やチャット、簡単なWebサイトの閲覧が中心の場合。
- 5GB〜10GB/月:地図アプリの利用や、画像の多いWebサイトの閲覧、クラウド上の資料確認など、外出先での利用が比較的多い場合。
- 20GB〜/月:Web会議への参加や、動画コンテンツの視聴、大容量のデータ送受信などを頻繁に行う場合。
まずはスモールスタートで少ない容量から契約し、実際の利用状況を見ながらプランを調整していくのが賢い方法です。

導入後の管理・運用を効率化するMDM(モバイルデバイス管理)とは?
タブレットを導入して終わり、ではありません。むしろ、導入後の管理・運用こそが、その効果を最大化し、セキュリティリスクを最小化するための鍵となります。特に数十台以上のタブレットを管理する場合、MDM(Mobile Device Management:モバイルデバイス管理)の導入はほぼ必須と言えるでしょう。ここでは、MDMで何ができるのか、なぜ必要なのかを分かりやすく解説します。
MDMで何ができる?主な機能を紹介
MDMとは、企業が社員に配布するスマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスを、情報システム部門などが一元的に、かつ遠隔で管理・監視・操作するためのツールです。MDMを導入することで、以下のようなことが可能になります。
- セキュリティポリシーの一括適用:全端末に同じパスワードポリシー(文字数や複雑さなど)を強制したり、画面ロックの時間を統一したりできます。
- アプリの配布・管理:業務に必要なアプリを管理者のPCから全端末に一括でインストール(配布)したり、逆に業務に不要なアプリ(ゲームなど)のインストールを禁止したりできます。
- 機能制限:カメラ機能やスクリーンショット機能、USB接続などを個別に無効化し、情報漏洩のリスクを低減します。
- リモートロック・リモートワイプ:端末を紛失・盗難された際に、管理者が遠隔で端末をロックして操作できないようにしたり、中のデータを完全に消去したりできます。これは最も重要な機能の一つです。
- 資産管理:各端末のOSバージョンやインストールされているアプリ、シリアル番号などの情報を一覧で把握し、管理台帳として活用できます。
なぜMDMが必要なのか?セキュリティリスクを具体的に解説
MDMを導入しない場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。例えば、ある社員がタブレットを電車に置き忘れてしまったとします。
MDMがない場合…
画面ロックをかけていなければ、第三者に端末内の顧客情報やメール、社内資料などを全て見られてしまいます。もし悪意のある人物に拾われたら、情報は抜き取られ、悪用されるかもしれません。会社はすぐに対応策を取ることができず、被害が拡大する可能性があります。
MDMがある場合…
社員からの紛失報告を受け、管理者は即座に管理画面からその端末をリモートロックします。これにより、第三者は端末を操作できなくなります。さらに、回収の見込みが低いと判断すれば、リモートワイプを実行し、端末内のデータを完全に消去。これにより、最悪の事態である情報漏洩を防ぐことができます。
このように、MDMは万が一のインシデントが発生した際の「保険」として、企業の重要な情報資産を守るために不可欠なツールなのです。
おすすめのMDMツール3選
世の中には多くのMDMツールが存在しますが、ここでは国内で実績の多い代表的なツールを3つご紹介します。
| ツール名 | 提供会社 | 特徴 | 料金目安(月額/1台) |
|---|---|---|---|
| CLOMO MDM | 株式会社アイキューブドシステムズ | 国内MDM市場でトップシェアを誇る。純国産で日本のビジネス環境に合ったきめ細やかな機能とサポートが魅力。 | 300円~ |
| Optimal Biz | 株式会社オプティム | AIを活用した独自機能や、PCも含めた統合的なデバイス管理に強みを持つ。コストパフォーマンスも高い。 | 250円~ |
| Jamf Pro | Jamf | Appleデバイス(iPhone, iPad, Mac)の管理に特化したMDM。Apple製品で統一している企業には最も強力な選択肢。 | 要問い合わせ |
MDMの導入には、ライセンス費用として端末1台あたり月額数百円のコストがかかります。しかし、情報漏洩によって失う社会的信用や損害賠償額を考えれば、これは非常に安価なセキュリティ投資と言えるでしょう。タブレット導入とセットで、MDMの検討も必ず進めるようにしてください。
【業種別】法人タブレット活用事例とおすすめモデル
タブレットは非常に汎用性の高いツールですが、業種によってその活用方法は様々です。「自分の業界では、具体的にどう役立つの?」という疑問にお答えするため、ここでは4つの業種をピックアップし、具体的な活用事例と、その用途に合ったおすすめのタブレットモデルをご紹介します。
飲食・小売業:POSレジ、オーダー端末としての活用
- 活用事例:
飲食店では、iPadをPOSレジとして活用する「モバイルPOS」の導入が急速に進んでいます。従来の大型レジに比べて省スペースで導入コストも安く、売上データをリアルタイムで分析できるのが強みです。また、お客様がテーブルのタブレットで注文する「セルフオーダーシステム」は、ホールスタッフの負担を軽減し、注文の機会損失を防ぎます。アパレルなどの小売店では、スタッフがタブレットを持ち、その場で在庫確認や商品の詳細情報をお客様に見せるといった、接客品質の向上に役立っています。 - おすすめモデル:iPad (第10世代)
理由:モバイルPOSアプリやオーダーシステムアプリの多くがiPadOSに最適化されており、動作が安定しています。また、スタイリッシュなデザインは店舗の雰囲気を損ないません。周辺機器(レシートプリンターやカードリーダー)も豊富です。
建設・不動産業:図面確認、現場報告での活用
- 活用事例:
建設現場では、これまで大量の紙で持ち運んでいた図面をタブレットで一元管理。拡大・縮小が自由自在で、細かい部分の確認も容易になります。現場で撮影した写真を直接図面に貼り付けて報告書を作成したり、遠隔地にいる設計者と画面を共有しながら打ち合わせを行ったりと、業務効率が劇的に向上します。不動産業では、お客様を内見に案内する際、タブレットで物件の360度パノラマ写真や周辺環境の情報を提示することで、より魅力的なプレゼンが可能になります。 - おすすめモデル:Panasonic TOUGHBOOKシリーズ or iPad + 耐衝撃ケース
理由:屋外での利用が多く、落下や粉塵、水濡れのリスクがあるため、堅牢性が最も重要です。本格的なタフ性能を求めるならTOUGHBOOK、コストを抑えたい場合はiPadにMIL規格準拠の頑丈なケースを装着するという方法も有効です。
教育・学習塾:デジタル教材、オンライン授業での活用
- 活用事例:
GIGAスクール構想により、小中学校での一人一台タブレットは当たり前になりました。学習塾や専門学校でも、動画や音声を使ったインタラクティブなデジタル教材の活用が進んでいます。生徒は自分のペースで学習を進められ、教員は個々の学習進捗をデータで把握しやすくなります。また、オンライン授業の配信・受講端末としてもタブレットは最適で、場所を選ばない学習環境を提供します。 - おすすめモデル:Lenovo Tab M10 Plus or Microsoft Surface Go 3
理由:生徒に配布する場合、コストは最重要課題です。Androidタブレットは導入費用を大幅に抑えられます。一方で、レポート作成などでOfficeソフトの利用が前提となる場合は、PCと同じように使えるSurface Go 3が適しています。
医療・介護業界:電子カルテ、訪問介護記録での活用
- 活用事例:
病院では、医師や看護師がタブレットを持ち、ベッドサイドで患者情報や検査データを確認しながら回診を行います。これにより、紙カルテの運用に比べて情報共有が迅速かつ正確になります。訪問介護の現場では、ヘルパーが訪問先で受けたサービス内容や利用者の様子をその場でタブレットに入力。事務所に戻ってから報告書を作成する手間がなくなり、直行直帰も可能になります。 - おすすめモデル:iPad (第10世代) or 小型のWindowsタブレット
理由:医療・介護向けの業務用アプリはiPadOS対応のものが多く、セキュリティ面でも安心感があります。一方、既存の電子カルテシステムがWindowsベースの場合は、互換性のあるWindowsタブレットが必須となります。持ち運びやすさを考慮し、8〜10インチ程度のサイズが好まれます。

法人タブレットの契約に関するよくある質問(Q&A)
最後に、法人タブレットの契約を検討する際によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。これまでの内容の復習も兼ねて、疑問点をスッキリ解消しておきましょう。
回答:はい、多くのキャリアや販売代理店で1台から法人契約が可能です。ただし、契約台数によって適用される割引率が変わる「ボリュームディスカウント」が設定されている場合が多いため、複数台をまとめて契約する方が1台あたりのコストは安くなる傾向にあります。将来的な増台計画がある場合は、契約時に伝えておくと良いでしょう。
回答:法人契約の場合、一般的に「請求書払い(銀行振込)」と「口座振替」が主な支払い方法となります。一部のオンラインストアや販売店では法人名義のクレジットカード払いに対応している場合もあります。リース契約の場合は、リース会社指定の支払い方法(主に口座振替)となります。
回答:契約内容によって対応が異なります。
- 購入した場合:メーカーの保証期間内であれば無償修理の対象となります(過失による故障は除く)。保証期間外は有償修理です。業務を止めないためには、代替機貸し出しサービスなどが付いた法人向けの保守契約に別途加入することをおすすめします。
- リース・レンタルの場合:多くの場合、契約に動産保険が含まれており、故障時の修理・交換費用はリース・レンタル会社が負担します。代替機の提供もスムーズな場合が多いです。
回答:一概には言えませんが、MDMを導入し、OSを常に最新の状態に保っていれば、基本的なセキュリティは確保されると考えられています。特にiPadOSはセキュリティレベルが高く、アンチウイルスソフトは不要とされるのが一般的です。AndroidやWindowsの場合は、企業のセキュリティポリシーに応じて、法人向けのアンチウイルスソフトや、より高度な脅威に対応するEDR(Endpoint Detection and Response)製品の導入を検討すると、さらに安全性が高まります。
回答:はい、個人事業主の方でも法人契約(ビジネス契約)を結ぶことは可能です。契約時には、開業届の控えや確定申告書の写しなど、事業を証明する書類の提出を求められることが一般的です。法人契約を結ぶことで、個人利用分と事業利用分を明確に分けられるため、経費管理がしやすくなるというメリットがあります。
まとめ:最適な一台を見つけてビジネスを加速させよう!
今回は、法人契約で安いタブレットを導入するための方法について、機種の選び方から契約形態、さらにはコストを劇的に下げる裏ワザまで、網羅的に解説してきました。
最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 法人タブレットは、セキュリティやサポート面で個人向けモデルにはないメリットがある。
- 導入方法は「購入」「リース」「レンタル」の3種類。初期費用を抑えたいならリースがおすすめ。
- 安いタブレットを選ぶ際は、価格だけでなく「利用目的」「OS」「通信方法」「セキュリティ」「サポート」の5つのポイントを必ずチェックする。
- 新品にこだわらなければ、「中古タブレット」という選択肢がコスト削減に絶大な効果を発揮する。
- 導入後の管理・運用のためにMDM(モバイルデバイス管理)の導入もセットで検討する。
タブレットは、もはや一部の先進的な企業だけが使う特別なツールではありません。正しく選び、賢く活用すれば、あらゆる企業の業務効率を向上させ、競争力を高める強力な武器となります。
「何から手をつければいいか分からない…」という方は、まずはこの記事で紹介した「中古タブレット」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。特に、伊藤忠グループが運営する「にこスマ」なら、品質、保証、サポートの三拍子が揃っており、法人利用でも安心して導入できます。高品質な端末を低価格で手に入れ、スモールスタートでタブレット活用の第一歩を踏み出してみましょう。
この記事が、あなたの会社のビジネスをさらに加速させる一助となれば幸いです。