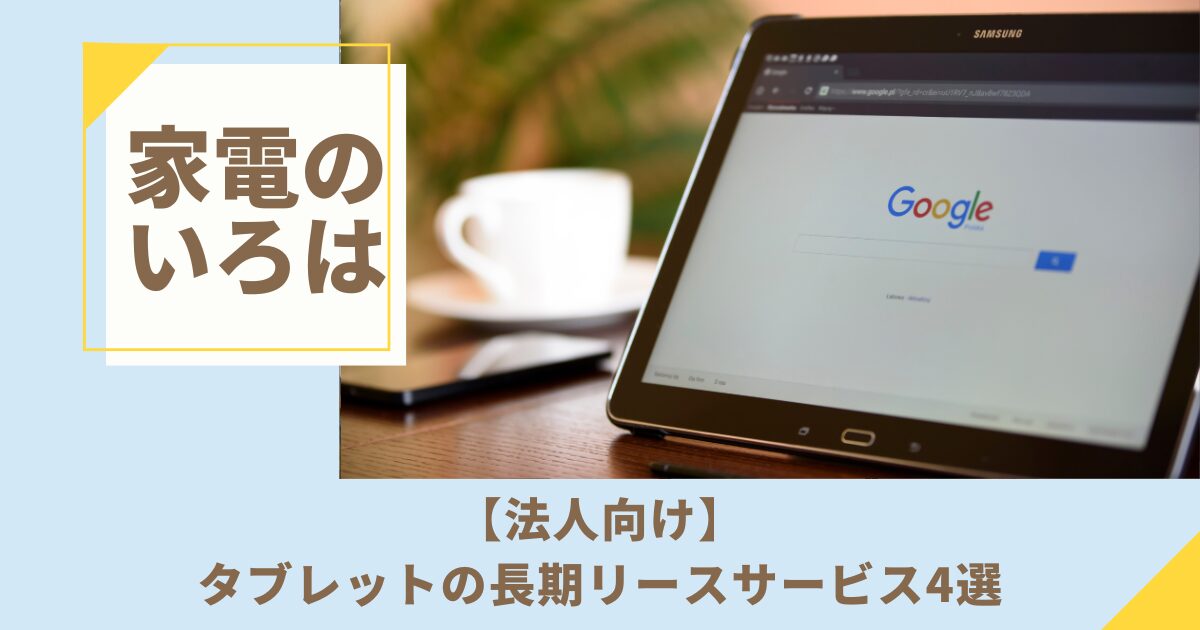「法人でタブレットを大量導入したいけど、初期費用が高すぎる…」
「社員のテレワーク用に、長期でタブレットを使いたいけど、どのサービスが良いかわからない…」
「管理やメンテナンスの手間を考えると、購入するべきかリースにすべきか悩む…」
このようなお悩みを抱えていませんか?
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や働き方の多様化により、法人でのタブレット活用は不可欠なものとなりつつあります。しかし、導入にはコストや管理面での課題がつきものです。
その強力な解決策となるのが、「タブレットの長期リース」です。
この記事では、法人向けのタブレット長期リースについて徹底解説します。おすすめのリース会社4選の比較から、料金相場、契約の注意点、さらにはレンタルや購入との違いまで、この記事を読めば、あなたの会社に最適なタブレット導入方法がすべてわかります。
コストを抑えつつ、業務効率を最大化する「賢い一手」を、この記事で見つけてください。
なぜ今、法人でタブレットの長期リースが注目されるのか?
まず初めに、なぜ多くの企業がタブレットの「購入」ではなく「長期リース」を選択しているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境にマッチした明確なメリットが存在します。テレワークの普及やDX推進といった時代の流れとともに、タブレットリースは単なるコスト削減策ではなく、企業の成長を加速させる戦略的な選択肢となっているのです。
テレワークやDX推進の加速
新型コロナウイルスの影響もあり、テレワークは多くの企業で標準的な働き方となりました。場所を選ばずに業務を遂行できるタブレットは、Web会議や資料共有、顧客へのプレゼンテーションなど、多様なシーンで活躍します。また、ペーパーレス化や業務プロセスのデジタル化といったDX推進においても、タブレットは中心的な役割を担います。こうした背景から、全社的に、あるいは部署単位で大量のタブレットを導入する需要が急速に高まっています。しかし、一度に数十台、数百台のタブレットを購入するとなると、莫大な初期投資が必要になります。長期リースは、この初期費用という大きなハードルを取り除き、企業の迅速なIT環境整備を可能にするのです。
初期費用を抑えられる大きなメリット
法人向けタブレット長期リースの最大のメリットは、なんといっても初期費用を大幅に抑えられる点です。購入する場合、例えば1台10万円のタブレットを50台導入すれば、500万円の初期費用がかかります。しかし、リースであれば月々の定額料金で使用を開始できるため、まとまった資金を用意する必要がありません。これにより、本来タブレット購入に充てるはずだった資金を、事業開発や人材投資など、他の重要な分野に回すことが可能になります。特に、資金繰りが重要な中小企業やスタートアップにとって、このメリットは計り知れない価値を持つでしょう。

煩雑な資産管理からの解放
タブレットを購入した場合、それらは企業の「固定資産」として計上されます。これには、資産台帳への登録、減価償却の計算、固定資産税の申告といった煩雑な会計処理が伴います。また、使用しなくなった際の廃棄処分にも手間とコストがかかります。一方、リース契約の場合、タブレットの所有権はリース会社にあるため、企業側での資産計上は不要です(※一部の会計基準を除く)。月々のリース料を「経費」として処理できるため、会計処理がシンプルになり、管理部門の負担を大幅に軽減できます。契約終了後は、リース会社に返却するだけで済むため、廃棄処分の心配もありません。
常に最新機種を利用できる利便性
IT機器の技術革新は日進月歩です。数年前に購入したタブレットでは、最新のアプリケーションが快適に動作しなかったり、セキュリティ面に不安が生じたりするケースも少なくありません。リース契約では、一般的に3年〜5年といった契約期間が設定されており、契約が満了するタイミングで新しい契約を結び、最新機種に入れ替えることが容易です。これにより、従業員は常に高性能で快適なデバイスを利用でき、生産性の向上につながります。また、セキュリティレベルの高い最新機種を使い続けることで、情報漏洩などのリスクを低減させる効果も期待できるのです。
【徹底比較】法人向けタブレット長期リースおすすめ4選
ここからは、いよいよ具体的な法人向けタブレット長期リースサービスをご紹介します。数あるサービスの中から、実績、サポート体制、プランの柔軟性などを総合的に評価し、特におすすめできる4社を厳選しました。それぞれの特徴を比較し、自社のニーズに最もマッチするサービスを見つけてください。
おすすめリース会社 比較一覧表
| サービス名 | 特徴 | おすすめの企業 |
|---|---|---|
| 大塚商会 (たよれーる) | 業界最大手。豊富な導入実績と全国をカバーする手厚いサポート体制が魅力。IT全般の相談が可能。 | IT担当者がいない、または手厚いサポートを求める中小企業。 |
| オリックス・レンテック | 取扱機種が豊富で、最新デバイスもいち早く提供。柔軟な契約プランが特徴。 | 特定の機種や最新モデルを導入したい企業。 |
| 横河レンタ・リース | キッティングサービス(初期設定)やデータ消去サービスに定評あり。セキュリティを重視する企業に強い。 | 情報システム部門の負担を軽減したい、セキュリティ要件が厳しい企業。 |
| SMFLレンタル (三井住友ファイナンス&リース) | 1台からの少台数リースにも対応。Webサイトでの手続きが簡便で、スピーディーな導入が可能。 | スタートアップや中小企業、特定の部署だけで少数導入したい企業。 |
1. 大塚商会 (たよれーる) – 圧倒的な実績と安心のサポート
法人向けITサービスの巨人、大塚商会が提供する「たよれーる」。その最大の魅力は、長年の経験で培われたノウハウと、全国を網羅する手厚いサポート体制です。タブレットのリースだけでなく、導入に関するコンサルティングから、ネットワーク構築、セキュリティ対策、導入後の運用サポートまで、ITに関するあらゆる悩みをワンストップで解決してくれます。「社内にIT専門の担当者がいない」という中小企業にとって、これほど心強いパートナーはいないでしょう。トラブル発生時も、電話一本で専門スタッフが迅速に対応してくれるため、安心して業務に集中できます。
2. オリックス・レンテック – 豊富な品揃えと柔軟性
オリックス・レンテックは、計測器などのレンタルで有名ですが、PCやタブレットのリースでも高い評価を得ています。特筆すべきは、その圧倒的な取扱機種の豊富さです。定番のiPadシリーズはもちろん、各社の最新AndroidタブレットやWindowsタブレットまで、幅広いラインナップから自社の用途に最適な一台を選べます。「特定の業務アプリを使うために、このスペックのタブレットが必要」といった専門的なニーズにも柔軟に対応可能です。また、契約期間や支払い方法に関しても相談しやすく、企業の状況に合わせた最適なプランを提案してくれます。
3. 横河レンタ・リース – 面倒な設定はすべてお任せ
「大量のタブレットを導入するのは良いが、一台一台の初期設定が大変…」そんな情報システム部門の悲鳴に応えてくれるのが、横河レンタ・リースです。同社は、キッティングサービス(初期設定代行)の品質が高いことで知られています。業務に必要なアプリのインストール、ネットワーク設定、セキュリティ設定などをすべて済ませた状態で納品してくれるため、従業員は箱から出してすぐにタブレットを使い始めることができます。また、リース終了後のデータ消去サービスも信頼性が高く、情報漏洩のリスクを徹底的に排除したい金融機関や大手企業からの支持が厚いです。

4. SMFLレンタル (三井住友ファイナンス&リース) – 1台からでもOK
三井住友ファイナンス&リースグループが展開するSMFLレンタルは、特に中小企業やスタートアップに優しいサービスと言えるでしょう。多くのリース会社が大口契約を主戦場とする中、同社は「1台から」という小ロットでのリースにも快く対応してくれます。「まずは役員用に数台だけ試してみたい」「特定のプロジェクトチームだけで使いたい」といったニーズにぴったりです。Webサイト上で見積もりから申し込みまで完結できる手軽さも魅力で、多忙な経営者や担当者の手間を省いてくれます。
気になる!タブレットのリース料金相場と内訳を解説
タブレットの長期リースを検討する上で、最も気になるのが「料金」ではないでしょうか。リース料金は、機種や契約期間、付帯サービスによって変動しますが、ある程度の相場を知っておくことで、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。ここでは、タブレットのリース料金相場と、その内訳について詳しく解説します。
【機種別】iPad・Androidタブレットの料金相場
リース料金は、当然ながら元となるタブレット本体の価格に大きく影響されます。以下に、一般的な機種ごとの月額リース料金の目安(3年契約の場合)をまとめました。
| 機種カテゴリ | 本体価格の目安 | 月額リース料金の目安 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| エントリークラスAndroid | 3万円~5万円 | 1,000円~2,000円 | Web閲覧、メール、簡単な資料確認など |
| iPad (無印) | 6万円~8万円 | 2,000円~3,500円 | 資料作成、Web会議、プレゼンテーションなど一般的なビジネス利用 |
| iPad Air / 上位Android | 9万円~12万円 | 3,000円~5,000円 | 動画編集、デザイン作成など、やや負荷のかかる作業 |
| iPad Pro | 13万円~ | 4,500円~ | 高度なクリエイティブ作業、CAD操作など専門的な業務 |
※上記はあくまで目安です。契約台数やオプションによって料金は変動します。
見ての通り、月々数千円の負担で高価なタブレットを利用できるのがリースの大きな魅力です。例えば、10万円のiPad Airを50台導入する場合、購入なら500万円の初期費用がかかりますが、リースなら月々20万円程度の経費で済みます(月額4,000円で計算)。この差は非常に大きいですよね。
料金に含まれるもの(本体、保守、保険など)
月額リース料金には、一体何が含まれているのでしょうか。基本的には以下の項目がパッケージになっていることがほとんどです。
- タブレット本体のレンタル料
- 契約期間中の保守・サポート費用(電話サポートなど)
- 動産総合保険料(偶発的な事故による破損、盗難などをカバー)
特に重要なのが「動産総合保険」です。従業員が誤ってタブレットを落下させて破損してしまったり、外出先で盗難に遭ってしまったりした場合でも、保険が適用されるため、修理費用や代替機の費用負担を大幅に軽減できます。購入した場合は、こうしたリスクに自社で備えなければならないため、保険が含まれている点はリースならではの安心材料と言えるでしょう。
オプション料金で何ができる?(キッティング、MDMなど)
基本料金に加えて、様々なオプションサービスを有料で追加できます。これらを活用することで、自社の運用に合わせたカスタマイズが可能です。
- キッティングサービス: 業務アプリのインストールや各種設定を代行。導入の手間を削減できます。(1台あたり数千円~)
- MDM (モバイルデバイス管理)導入支援: 複数台のタブレットを一元管理し、セキュリティポリシーの適用や遠隔でのデータ消去(リモートワイプ)などを可能にするツールの導入をサポートします。
- データ消去サービス: リース返却時に、端末内のデータを専門的な方法で完全に消去し、証明書を発行してくれます。情報漏洩対策に必須です。
- オンサイト保守: 故障時に技術者が直接訪問して修理や交換を行ってくれるサービスです。
コストを抑えるための料金交渉のコツ
リース料金は、ある程度の交渉が可能です。少しでもコストを抑えたい場合は、以下の点を意識してリース会社と交渉してみましょう。
- 相見積もりを取る: 必ず複数のリース会社から見積もりを取りましょう。「他社ではこのくらいの金額だった」という事実は、強力な交渉材料になります。
- 契約台数をまとめる: 当然ながら、契約する台数が多ければ多いほど、1台あたりの単価は下がりやすくなります。将来的な増設予定があるなら、それも伝えて交渉すると良いでしょう。
- 契約期間を長くする: 3年契約よりも5年契約の方が、月々のリース料金は安くなる傾向にあります。長期的な利用が確定している場合は、長めの契約期間を検討しましょう。
- 不要なオプションを外す: 見積もりに含まれているオプションが、本当に自社に必要かを見極めましょう。例えば、自社でキッティングできる体制があるなら、そのサービスは外すことでコストを削減できます。
法人向けタブレットリース契約の全手順と注意点
「リースが良さそうなのはわかったけど、手続きが面倒なのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、法人向けタブレットリースの契約プロセスは意外とシンプルです。ここでは、契約までの流れと、後で後悔しないために絶対に確認しておくべき注意点を詳しく解説します。
STEP1: ニーズの洗い出しと機種選定
まず最初に行うべきは、「何のために」「誰が」「どこで」タブレットを使うのかを明確にすることです。
- 利用目的: 営業先でのプレゼン? 工場での在庫管理? それとも役員会議でのペーパーレス化? 目的によって必要なスペックや画面サイズが変わります。
- 利用者: ITリテラシーの高い若手社員が中心か、それともPC操作が苦手なベテラン社員も使うのか。操作のしやすさも重要な選定基準です。
- 利用環境: 屋外での利用が多いなら、画面の明るさやバッテリー性能が重要になります。Wi-Fi環境のない場所で使うなら、セルラーモデル(SIMカードが使えるモデル)を選ぶ必要があります。
これらのニーズを基に、OS(iPadOS, Android, Windows)や機種を絞り込んでいきます。この段階でリース会社に相談すれば、プロの視点から最適な機種を提案してもらうことも可能です。
STEP2: リース会社への見積もり依頼
機種と大まかな台数が決まったら、複数のリース会社に見積もりを依頼します。前の章で紹介したようなリース会社に問い合わせてみましょう。その際、以下の情報を伝えるとスムーズです。
- 希望する機種、台数
- 希望するリース期間(例: 3年、5年など)
- 必要なオプションサービス(キッティング、MDMなど)
- 納品希望時期
複数の見積もりを比較検討し、料金だけでなく、サポート体制や担当者の対応なども含めて、総合的に判断することが重要です。
STEP3: 審査と契約手続き
依頼するリース会社が決まったら、正式に申し込みを行います。リース契約には、リース会社の与信審査が必要です。一般的に、企業の財務状況(決算書など)や事業内容が審査されます。特に設立間もない企業や、債務超過の企業の場合は審査が厳しくなることもあります。審査に通過すれば、契約書を取り交わします。契約内容を隅々まで確認し、不明な点があれば必ず担当者に質問しましょう。
STEP4: 納品と利用開始
契約が完了すると、指定した日時にタブレットが納品されます。キッティングサービスを依頼していれば、設定済みの状態で届くのですぐに利用を開始できます。納品されたら、機種や台数に間違いがないか、正常に動作するかを必ず検品しましょう。ここから、月々のリース料の支払いがスタートします。
【重要】契約前に必ずチェックすべき5つの項目
契約書にサインする前に、以下の5つの項目は必ず確認してください。ここを見落とすと、後々「こんなはずじゃなかった」というトラブルになりかねません。
- 契約期間と中途解約の条件: リース期間は何年か、そして原則として中途解約はできないという点を理解しておく必要があります。万が一、事業の縮小などでタブレットが不要になった場合でも、残りの期間のリース料を一括で支払う(違約金が発生する)ことがほとんどです。
- 再リース料: 契約期間が満了した後も、同じタブレットを継続して使いたい場合、「再リース契約」を結ぶことになります。その際の再リース料(一般的には年間リース料の1/10程度)がいくらになるのかを事前に確認しておきましょう。
- 保険の適用範囲と免責金額: 故障や盗難をカバーしてくれる動産総合保険ですが、その適用範囲には限界があります。例えば、故意による破損や、地震・噴火・津波などの天災による損害は対象外となることが多いです。また、保険を利用する際に自己負担となる「免責金額」が設定されているかも確認が必要です。
- 修繕義務の所在: 通常の利用範囲での故障(自然故障)はリース会社の負担で修理してもらえますが、利用者の過失による破損の修理費用はどちらが負担するのか、契約書で明確にしておきましょう。
- 契約終了時の扱い: 契約が終わったタブレットは「返却」が基本ですが、オプションで「買い取り」が可能な契約もあります。また、返却する際のデータ消去は誰の責任で行うのか(自社か、リース会社か)も重要な確認ポイントです。

レンタル・購入・中古購入との違いは?メリット・デメリットを比較
法人でタブレットを導入する方法は、長期リースだけではありません。「短期レンタル」「新品購入」「中古購入」といった選択肢もあります。自社にとって最適な方法を選ぶためには、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解することが不可欠です。ここでは、それぞれの特徴を表で比較し、詳しく解説していきます。
【表で比較】リース vs レンタル vs 購入 vs 中古
| 長期リース | 短期レンタル | 新品購入 | 中古購入 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用期間 | 長期(1年~5年) | 短期(1日~数ヶ月) | 制限なし | 制限なし |
| 初期費用 | ◎ 不要 | ◎ 不要 | △ 高額 | ○ 安い |
| 月額費用 | ○ 安い | △ 割高 | × なし(一括払い) | × なし(一括払い) |
| 所有権 | リース会社 | レンタル会社 | 自社 | 自社 |
| 機種選定 | ○ 比較的自由 | △ 制限あり | ◎ 自由 | △ 在庫次第 |
| 資産管理 | ◎ 不要(楽) | ◎ 不要(楽) | △ 必要(煩雑) | △ 必要(煩雑) |
| 中途解約 | × 原則不可 | ○ 可能 | – | – |
長期利用ならリースが断然お得な理由
1年以上の長期にわたってタブレットを利用することが決まっている場合、最もコストパフォーマンスと管理効率のバランスが良いのが長期リースです。購入のように莫大な初期投資は不要で、月々の支払額も短期レンタルに比べて格段に安く設定されています。また、資産管理の手間がかからない点、契約終了時に最新機種へ入れ替えやすい点も、変化の速いビジネス環境において大きなメリットとなります。
短期利用やイベントならレンタルが最適
数日間だけのイベントや研修、あるいは数ヶ月間の短期プロジェクトでタブレットが必要な場合は、短期レンタルが最適です。リースと違って、必要な期間だけ借りることができ、中途解約も可能です。ただし、月額(あるいは日額)の料金はリースよりも割高に設定されているため、長期間の利用には向きません。「必要な時に、必要な数だけ」スポットで利用したいケースに限定した選択肢と考えるべきでしょう。
資産として保有したいなら購入という選択肢
初期費用はかかりますが、タブレットを自社の資産として保有したい場合は、新品購入が選択肢となります。リースのように契約期間に縛られることなく、長期間使い続けることができますし、カスタマイズも自由に行えます。ただし、前述の通り、固定資産としての会計処理や、故障時の修理手配、廃棄処分などをすべて自社で行う必要があります。情報システム部門の体制が整っており、資産管理の負担を許容できる大企業などに向いている方法です。
コストを極限まで抑えるなら「中古タブレット購入」も視野に
「リースやレンタルは便利だけど、毎月の支払いが発生するのが気になる…」「できる限りトータルの費用を抑えたい!」
そんな企業様にご提案したいのが、「高品質な中古タブレットの購入」という第4の選択肢です。
中古と聞くと、「すぐに壊れそう」「バッテリーが劣化してそう」「セキュリティは大丈夫?」といった不安を感じるかもしれません。しかし、信頼できる販売店から購入すれば、そうした心配は無用です。
そこでおすすめしたいのが、伊藤忠商事グループの株式会社Belongが運営する中古スマホ・タブレットのECサイト「にこスマ」です。
「にこスマ」では、法人向けの大量購入にも対応しており、リースや新品購入に代わる非常に魅力的な選択肢となります。

- 圧倒的なコスト削減: なんといっても最大のメリットは価格です。新品に比べて大幅に安い価格で、高性能なタブレットを導入できます。これにより、同じ予算でより多くの台数を揃えたり、ワンランク上のスペックの機種を導入したりすることが可能になります。
- 厳しい基準をクリアした高品質端末: 「にこスマ」で販売されている端末は、画面や本体に割れ・欠けがないものを厳選。さらに、最先端の検査システムによって25項目以上の機能検査をクリアした、高品質な端末のみを取り扱っています。中古でも安心して業務に利用できます。
- 安心の1年保証: 万が一、端末に不具合があった場合でも、1年間の無料返品交換保証が付いています(※一部対象外あり)。これは、品質に対する自信の表れです。電話やチャットでのサポート体制も整っており、導入後も安心です。
- 全キャリア対応で手間いらず: 取り扱っているのはネットワーク利用制限がなく、SIMフリーの端末のみ。どの通信キャリアのSIMカードでも利用できるため、通信契約に関する手間や心配がありません。
リース契約の審査が通らなかった企業や、できるだけ早く、かつ安価にタブレットを資産として確保したい企業にとって、「にこスマ」での中古タブレット購入は非常に賢い選択と言えるでしょう。ぜひ一度、公式サイトで豊富な品揃えと価格をチェックしてみてください。
【必見】法人リースで失敗しないタブレット機種の選び方
リースするサービスが決まっても、次に悩むのが「どのタブレットを選べば良いのか」という点です。市場には多種多様なタブレットがあり、自社の業務に合わないものを選んでしまうと、せっかく導入しても「使いにくい」「動作が遅い」といった不満が噴出し、宝の持ち腐れになりかねません。ここでは、法人利用の観点から、失敗しないタブレット機種の選び方を4つのポイントに分けて解説します。
OSで選ぶ(iPadOS vs Android vs Windows)
タブレットの使い勝手を大きく左右するのがOS(オペレーティングシステム)です。それぞれに特徴があるため、用途に合わせて選びましょう。
- iPadOS (Apple):
- メリット: 直感的で誰にでも分かりやすい操作性、豊富で質の高いアプリ、セキュリティの高さ、デザイン性の高さ。
- デメリット: 本体価格が比較的高価、カスタマイズ性が低い。
- おすすめの用途: クリエイティブな作業(デザイン、動画編集)、顧客へのプレゼンテーション、教育現場での利用など。操作が簡単なため、IT機器に不慣れな従業員が多い場合にもおすすめです。
- Android (Google):
- メリット: 様々なメーカーから多様な価格帯・スペックの機種が発売されており、選択肢が豊富。カスタマイズ性が高く、Google系のサービスとの連携がスムーズ。
- デメリット: 機種によって操作性や性能にばらつきがある、セキュリティ面でiPadOSにやや劣るという意見も。
- おすすめの用途: 特定の業務用アプリの利用(専用アプリがAndroidのみ対応の場合など)、Google Workspaceをメインで利用している企業、コストを重視する場合。
- Windows (Microsoft):
- メリット: 普段使っているパソコンと同じ感覚で操作できる。Microsoft Officeとの親和性が非常に高い。USBポートなど拡張性が高いモデルが多い。
- デメリット: タブレット専用アプリが少ない、タブレットとしての操作性は他のOSに劣る場合も。
- おすすめの用途: 外出先でもExcelやWord、PowerPointをPCと同じように使いたい営業職など。2-in-1モデル(キーボード着脱式)を選べば、ノートPCのようにも使えます。
サイズと重量で選ぶ(携帯性 vs 視認性)
タブレットは持ち運んで使うことが多いからこそ、サイズと重量は重要な選定ポイントです。
- 7~8インチクラス:携帯性重視。片手で持てるサイズ感で、店舗での注文取り(ハンディ端末)や、工場内での作業マニュアル確認など、常に持ち歩きながら使う用途に最適です。ただし、画面が小さいため、長時間の資料作成などには向きません。
- 10インチ前後クラス:携帯性と視認性のバランスが最も良い、標準的なサイズです。Web会議、資料閲覧、プレゼンテーションなど、幅広いビジネスシーンに対応できます。法人向けで最も多く選ばれているサイズ帯です。
- 12インチ以上クラス:視認性・作業性重視。ノートPCに近い大画面で、図面(CAD)の確認やデザイン作業、複数のウィンドウを開いての作業などに適しています。その分、重くかさばるため、携帯性は劣ります。
スペックで選ぶ(CPU、メモリ、ストレージ)
「動作がカクカクしてストレス…」とならないために、最低限のスペックは確認しておきましょう。専門用語が多くて難しく感じるかもしれませんが、ポイントを絞れば大丈夫です。
- CPU: タブレットの「頭脳」にあたる部分。性能が高いほど処理速度が速くなります。Web閲覧やメールが中心ならエントリークラスでも十分ですが、複数のアプリを同時に使ったり、重いデータを扱ったりするなら、ミドルクラス以上のCPUを搭載したモデルを選びましょう。
- メモリ (RAM): 作業机の広さに例えられます。メモリが大きいほど、多くのアプリを同時に開いても動作が安定します。法人利用であれば、最低でも4GB、快適に使いたいなら8GB以上を推奨します。
- ストレージ: データやアプリを保存する「倉庫」の容量です。最近はクラウドストレージの利用が主流なので、本体のストレージはそこまで大容量でなくても良いケースが多いですが、オフラインで大容量の動画や設計データを扱う場合は、128GB以上のモデルを選ぶと安心です。
セキュリティ機能で選ぶ(MDM対応など)
法人利用では、個人利用以上にセキュリティ対策が重要です。万が一の紛失・盗難に備え、以下の機能に対応しているかを確認しましょう。
- 生体認証: 指紋認証や顔認証に対応しているモデルであれば、パスワード入力の手間なく、安全にロックを解除できます。
- MDM (モバイルデバイス管理)対応: MDMツールを導入することで、管理者は遠隔で多数のタブレットを一元管理できます。アプリのインストールを制限したり、紛失時に遠隔でデータを消去(リモートワイプ)したりと、企業のセキュリティポリシーを徹底させるために必須の機能です。リース会社がMDMの導入支援を行っている場合も多いので、合わせて相談してみましょう。
学校・教育機関向けタブレットリースの特徴と導入事例
法人向けタブレットリースの需要は、一般企業だけでなく、学校や大学といった教育機関でも急速に高まっています。特に「GIGAスクール構想」をきっかけに、児童・生徒一人一台のタブレット環境を整備する動きが全国的に加速しました。ここでは、学校・教育機関ならではのタブレットリースの特徴と、実際の導入事例について掘り下げていきます。
GIGAスクール構想とタブレット導入の現状
GIGAスクール構想とは、文部科学省が推進する、全国の小中学校で「児童・生徒一人一台の学習者用端末」と「高速大容量の通信ネットワーク」を一体的に整備する構想です。これにより、個別最適化された学びや、創造性を育む教育の実現を目指しています。この構想の実現のために、多くの自治体や学校がタブレットの大量導入を進めていますが、その導入方法としてリース契約が広く活用されています。
購入ではなくリースが選ばれる理由としては、やはり「初期費用の平準化」が大きいです。数千台、数万台規模のタブレットを一度に購入するには莫大な予算が必要ですが、リースであれば年度ごとの予算内で計画的に導入を進めることができます。また、数年ごとに最新機種に入れ替えられるため、陳腐化を防ぎ、常に快適な学習環境を維持できる点も評価されています。
学校向けプランの特別料金やサポート体制
多くのリース会社では、一般企業向けとは別に、学校・教育機関向けの特別プランを用意しています。
- 特別価格(アカデミックプライス): AppleやMicrosoftなどが提供する教育機関向けの割引価格を適用することで、通常よりも安いリース料金が設定されている場合があります。
- GIGAスクール構想対応パッケージ: タブレット本体だけでなく、充電保管庫、学習支援ソフト、教員向けの研修などをセットにしたパッケージプランを提供している会社もあります。
- 手厚いサポート: 先生方が授業に集中できるよう、導入時の設定支援や、故障時の代替機即日発送サービス、ヘルプデスクの設置など、手厚いサポート体制が組まれているのが特徴です。
- フィルタリングサービス: 児童・生徒が有害なサイトにアクセスしないよう、Webサイトのフィルタリングサービスが標準で付帯していることがほとんどです。

導入事例1: A小学校での授業活用例
A小学校では、全学年の児童にiPadをリースで導入しました。導入前は、調べ学習の際に図書室の限られたPCを順番待ちで利用していましたが、導入後は各教室でいつでもインターネットに接続できるようになり、児童が主体的に情報を収集し、まとめる力が飛躍的に向上しました。また、デジタルドリルアプリを活用することで、一人ひとりの習熟度に合わせた問題に取り組めるようになり、学力向上にもつながっています。故障時にはリース会社のサポートデスクが迅速に対応してくれるため、授業が滞る心配もありません。
導入事例2: B大学での研究活動への応用
理系の研究室を持つB大学では、高性能なiPad Proをリースで導入。従来は紙の実験ノートに手書きで記録していましたが、タブレットを導入したことで、実験データの記録、写真や動画での観察記録、関連論文の閲覧などをシームレスに行えるようになりました。これにより、研究データの管理が効率化され、学生たちの研究活動の質が向上しました。リース契約のため、数年後にはさらに高性能な最新モデルに入れ替える予定で、常に最先端の研究環境を維持できると教員からも好評です。
教育機関がリースを選ぶ際の注意点
学校・教育機関がリース契約を結ぶ際には、一般企業とは異なる注意点があります。
- 自治体の予算制度との整合性: 公立学校の場合、単年度会計が原則のため、複数年度にわたるリース契約が予算制度上可能かどうか、事前に自治体の会計課や教育委員会に確認する必要があります(債務負担行為の設定など)。
- 補助金の活用: GIGAスクール構想関連の補助金などを活用する場合、その補助金の対象となる契約形態かどうかをしっかりと確認する必要があります。
- セキュリティと管理体制: 多数の児童・生徒が利用するため、MDMによる一元管理や、紛失・盗難時のルール作り、情報モラル教育の徹底など、厳格な管理体制の構築が不可欠です。
個人事業主・フリーランスでもタブレットリースは可能?
ここまで主に「法人」向けのタブレットリースについて解説してきましたが、「個人事業主やフリーランスでもリース契約はできるの?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、個人事業主でもタブレットのリース契約は可能です。しかし、法人契約とは異なる点や、審査における注意点が存在します。
個人事業主がリース契約を結ぶための条件
個人事業主がリース契約を申し込む場合、基本的には「事業用としての利用」が前提となります。プライベートでの利用を目的とした契約はできず、あくまで事業の用に供するための設備投資として扱われます。申し込みの際には、屋号や事業内容、事業の実態を示す書類(開業届の写しや確定申告書の控えなど)の提出を求められることが一般的です。
審査でチェックされるポイントとは?
リース会社が行う与信審査では、法人とは少し異なる視点でチェックが行われます。
- 事業の安定性・継続性: 事業を始めてからの年数(事業歴)や、確定申告書から読み取れる売上・所得の状況が重視されます。事業を開始して間もない場合や、所得が不安定な場合は、審査が厳しくなる傾向にあります。
- 個人の信用情報: 個人事業主の場合、代表者個人の信用情報(クレジットカードやローンの支払い履歴など)が照会されることがあります。過去に支払いの延滞などがあると、審査に影響する可能性があります。
- 事業内容の具体性: なぜ事業にタブレットが必要なのか、どのように活用するのかを具体的に説明できると、審査においてプラスに働くことがあります。
もし審査に不安がある場合は、まずは1台から契約できるリース会社や、個人事業主向けのプランに力を入れている会社に相談してみるのが良いでしょう。

個人向けレンタルサービスとの比較
もしリース契約の審査が通らなかったり、より手軽に利用したかったりする場合は、「個人向けのレンタルサービス」も選択肢になります。DMMいろいろレンタルやRentio(レンティオ)といったサービスでは、個人名義でクレジットカードがあれば、比較的簡単にタブレットをレンタルできます。
ただし、これらのサービスは数日~数ヶ月単位の短期利用を想定しているため、1年以上の長期で利用する場合は、事業用のリース契約を結ぶよりもトータルコストが割高になることがほとんどです。事業で長期間使うことが確定しているなら、やはりリース契約を目指すのが最も経済的と言えます。
確定申告での経費計上の方法
個人事業主がタブレットをリースした場合、その月々のリース料は、全額を「賃借料」や「リース料」といった勘定科目で経費として計上できます。購入した場合のように、固定資産として計上し、減価償却を行う必要がないため、会計処理が非常にシンプルになるというメリットがあります。
これは、節税の観点からも有利に働く場合があります。特に、事業開始年度などで利益が多く出そうな年にリースを始めれば、その年の所得を圧縮する効果が期待できます。確定申告の際には、リース会社から送られてくる支払明細書や請求書を保管しておき、経費の証憑としましょう。
タブレットのリースに関するよくある質問 Q&A
ここでは、法人向けタブレットリースを検討している担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。契約前の最後の疑問解消にお役立てください。
リース期間が満了した際の選択肢は、主に以下の3つです。
- 新しい機種で再契約: これまで使っていたタブレットを返却し、新たに最新機種でリース契約を結び直します。常に最新の環境を維持したい場合に最も一般的な選択肢です。
- 再リース(継続利用): 今使っているタブレットを、割安な料金(一般的に年間リース料の1/10程度)で継続して利用します。まだ十分に使える、使い慣れた機種をそのまま利用したい場合に選択します。
- 返却して契約終了: タブレットをリース会社に返却し、契約を完全に終了します。
一部の契約では「買い取り」オプションが付いている場合もありますが、一般的ではありません。どの選択肢が取れるかは契約内容によるため、事前に確認しておきましょう。
まずは、速やかに契約しているリース会社に連絡してください。
- 故障の場合: 通常の利用範囲での自然故障であれば、リース会社の負担で修理または交換が行われます。従業員の過失(落下など)による破損の場合は、契約に含まれる動産総合保険が適用されることが多いです。ただし、免責金額(自己負担額)が設定されている場合があるので注意が必要です。
- 紛失・盗難の場合: こちらも動産総合保険の対象となることが多いですが、警察への届け出(盗難届など)が必要になります。保険が適用された場合でも、本体価格の一部を負担する必要があるケースもあります。何よりも、情報漏洩を防ぐため、MDMなどを利用して遠隔で端末をロックしたり、データを消去したりする(リモートワイプ)措置を迅速に行うことが重要です。
リース会社が行うのは、あくまで「機器の提供」と「ハードウェアの保守」が基本です。ウイルス対策ソフトの導入や、MDMによる運用管理、従業員への情報セキュリティ教育など、日常的なセキュリティ対策の実施責任は、利用者である企業側にあります。
ただし、多くのリース会社では、オプションサービスとしてセキュリティソフトの提供やMDMの導入・運用支援サービスを用意しています。自社に専門知識を持つ担当者がいない場合は、こうしたオプションを積極的に活用することをおすすめします。
- 増やす場合(追加リース): 契約途中でも、新たに追加でリース契約を結ぶことで台数を増やすことは可能です。ただし、契約開始時期が異なるため、元の契約とは別の管理番号で扱われることが一般的です。
- 減らす場合(中途解約): 前述の通り、リース契約は原則として中途解約ができません。そのため、途中で台数を減らすことは非常に困難です。もし不要になった場合は、残りの期間のリース料を一括で支払う必要があります。導入台数は、慎重に計画を立てて決定することが重要です。
リースと割賦(分割払いでの購入)は、どちらも月々の支払いで機器を導入できる点では似ていますが、法的な性質が全く異なります。
- リース: あくまで「賃貸借契約」です。所有権はリース会社にあり、月々の支払いは経費として処理します。契約終了後は返却するのが基本です。
- 割賦(分割払い): 「売買契約」です。支払いが完了すれば、所有権は自社に移転します。そのため、機器は固定資産として計上し、減価償却を行う必要があります。
会計処理の簡便さや、常に最新機種を使いたいというニーズがあるならリース、最終的に自社の資産として所有したいなら割賦(購入)が適しています。
まとめ:最適なタブレットの長期リースでビジネスを加速させよう
今回は、法人向けのタブレット長期リースについて、メリット・デメリットからおすすめのサービス、料金、契約の注意点まで、網羅的に解説してきました。
最後に、本記事の重要なポイントをもう一度確認しておきましょう。
- タブレットの長期リースは、初期費用を抑え、資産管理の手間を省ける、現代のビジネス環境に最適な導入方法である。
- リース会社を選ぶ際は、料金だけでなく、サポート体制やキッティングなどの付帯サービスを総合的に比較することが重要。
- 契約前には、中途解約の条件や保険の適用範囲などを必ず確認し、後々のトラブルを防ぐ。
- 利用目的や利用者に合わせて、OS・サイズ・スペックを慎重に選定することが、導入成功のカギ。
- コストを極限まで抑えたい場合は、「にこスマ」のような信頼できる中古タブレットの購入も非常に有効な選択肢となる。
タブレットの導入は、もはや一部の先進的な企業の取り組みではありません。ペーパーレス化によるコスト削減、テレワークによる多様な働き方の実現、業務効率化による生産性の向上など、企業の成長に不可欠な経営戦略の一つとなっています。
「うちの会社にはまだ早いかも…」と考えているうちに、競合他社はどんどん先へ進んでしまうかもしれません。
この記事を読んで、タブレットの長期リースに少しでも可能性を感じたなら、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。まずは、今回ご紹介したリース会社の中から気になる数社に問い合わせて、無料の見積もりを取ることから始めてみましょう。自社の課題を相談する中で、きっと最適な導入プランが見えてくるはずです。
最適なタブレット導入が、あなたの会社のビジネスを次のステージへと押し上げる強力なエンジンとなることを願っています。